
阪急東通商店街が、人でいっぱい。
晩ご飯は、久しぶりに「御岳さん」に行く。
大将が「まいど」と挨拶してくれる。
(食べログ)

おでんを3品(スジ、大根、厚揚げ)を頼む。

メニューをよく見ると、「たぬき」のほかに「江戸たぬき」と「京たぬき」があることに気づいた。
今回は、「江戸たぬき」(550円)を頼む。
天かすと月見の入ったそば。
次回は、「京たぬき」を頼もう。

梅田散歩

阪急東通商店街が、人でいっぱい。
晩ご飯は、久しぶりに「御岳さん」に行く。
大将が「まいど」と挨拶してくれる。
(食べログ)

おでんを3品(スジ、大根、厚揚げ)を頼む。

メニューをよく見ると、「たぬき」のほかに「江戸たぬき」と「京たぬき」があることに気づいた。
今回は、「江戸たぬき」(550円)を頼む。
天かすと月見の入ったそば。
次回は、「京たぬき」を頼もう。

此花区の温泉「上方温泉一休」の送迎バス。
西九条まで送ってくれる。
寒い。

西九条のラーメン屋さん「白馬童子」。
大阪市営バスが通る道路わきにある。

阪神電車の車掌さんが雑誌で紹介しているページが貼ってある。

名物の「しあわせラーメン」。
チャーシュー3枚と煮玉子が入ったとんこつ味のラーメン(680円)
なかなか美味しい。

餃子(250円)は、普通の味。

西九条からは、JRで2駅、大阪へ帰る。

本町の「炭火七輪焼き 鶏motto」でランチ。
チェーン店のようだ。
(食べログ)

1Fはカウンター席。
夜は、ここで七輪で鶏を焼くようだ。
帽子のお姉さんが、店長さん。

鶏のから揚げと鶏肉メンチカツの定食(800円)
熱々で美味しい。鶏肉のメンチカツもいい。

難波神社の裏の通りの角の雑居ビルの1Fに、古本屋「Colombo(コロンボ)」がある。
ホームページは、お知らせだけのページ。

「BUY SELL BOOKS, VINTAGE,FRESH COFFEE」と書いてある。
写真、建築、美術関係の本がたくさん。
古い雑誌も置いてある。
コーヒーは、外のテーブルで飲むみたいだ。
地図を載せます。
[google-map-v3 width=”400″ height=”400″ zoom=”16″ maptype=”roadmap” mapalign=”left” directionhint=”false” language=”ja” poweredby=”false” maptypecontrol=”true” pancontrol=”true” zoomcontrol=”true” scalecontrol=”true” streetviewcontrol=”true” scrollwheelcontrol=”true” draggable=”true” tiltfourtyfive=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkerlist=”34.679117,135.499578{}coffee.png{}古本 Colombo” bubbleautopan=”true” showbike=”false” showtraffic=”false” showpanoramio=”false”]
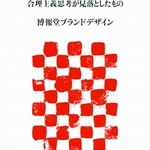
『ビジネスは「非言語」で動く 合理主義思考が見落としたもの』 博報堂ブランドデザイン を読む。
一冊の本にするには、まとまりのない文章。事例紹介だけの本。
「本書のまとめ」部分がまとまっている。
人間は、意識して考えている以上のことを感じている。そして、その感じる世界には、言語という道具だけではとらえきれない部分がある。そんなまだ十分に活用できていない豊かな世界を活かすためにも、非言語領域に着目し、それを活かすと決断し、使いこなす手法を身につけようということだ。
非言語領域をビジネスに活用することができれば、ビジネスは「言語」だけの世界のものではなくなる。「人間」そのものの世界のものになる。ビジネスが人間化されていく。非言語領域にこそ、いまビジネスが直面している行き詰まりをブレイクスルーする手がかりがあるのではないか。ひとことで言えば、それが本書の提案である。
豊かなイメージを伝えることができる「たとえ」を通じて、私たちが感じ取っている豊かな感覚の世界。これを自分自身で意識の上にはっきりと乗せることで、非言語領域を活かしながらよりよいコミュニケーションをとることができる。
いわゆる「仕事のできる人」は、自分の非言語領域、相手の非言語領域を汲み取ったうえで物事を進めており、それがよい結果を生んでいるという話だ。
逆にこの領域への配慮が足らないと、実際に行動に移す段階でいろいろと問題が生じるということにも触れた。そして現代は、なにかと「理由」を大切にする時代であり、その結果、非言語領域への配慮がおろそかになっているとも述べた。背景にあるのは分業と、そこから派生する恐れという感情(非言語領域)である。