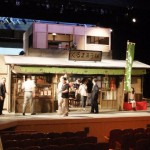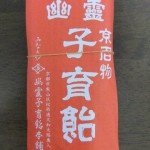心斎橋の西隣、南船場を散策。
熊、うさぎ、河童などのキャラクターの看板のお店を発見。
アランジアロンゾ(あらんじあろんぞ、aranziaronzo)という聞きなれない名前のお店。
Wikipedia で調べると 姉妹である斎藤絹代・余村洋子2人のオリジナル雑貨作製ユ ニット名。その商品のブランド名でもあり、社名でもある。特にその数々のオリジナルキャラクター作家として知られており、「かわいくてへんてこでかっこよ くてばかばかしくてちょっとこわくてまぬけでなごめる」作風で若い女性と子供に人気があるそうだ。

店の中には、若い女性がちらほら。

店内は、キャラクターグッズがいっぱい。

弁当箱の絵が笑える。
パンダは、もぐもぐ、猫は口をぬぐっている。
こんな人いるなぁという絵。

袋物などは、数百円からある。

窓側にもいろいろ飾ってある。
女性の店員さんが1名で店番。
東京スカイツリー(SuperFancyShop)にも店を出しているそうです。
[google-map-v3 width=”400″ height=”400″ zoom=”16″ maptype=”roadmap” mapalign=”left” directionhint=”false” language=”japanese” poweredby=”false” maptypecontrol=”true” pancontrol=”true” zoomcontrol=”true” scalecontrol=”true” streetviewcontrol=”true” scrollwheelcontrol=”false” draggable=”true” tiltfourtyfive=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkermashupbubble=”false” addmarkerlist=”34.677282,135.497965{}supermarket.png{}ARANZI ARONZO (http://www.aranziaronzo.com/)” bubbleautopan=”true” showbike=”false” showtraffic=”false” showpanoramio=”false”]