山村 修 『<狐>が選んだ入門書』 ちくま文庫 を読む。
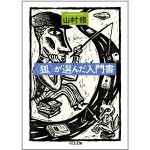
入門書こそ究極の読みものである。
私のいう入門書は、それ自体、一個の作品である。ある分野を学ぶための補助としてあるのではなく、その本そのものに、すでに一つの文章世界が自律的に開かれている。思いがけない発見にみち、読書のよろこびにみちている。私が究極の読みものというとき、それはそのような本を指しています。
第一章 言葉の居住まい
1.国語辞典に「黄金」を掘りあてる
武藤 康史 『国語辞典の名解釈』
2.敬語は日本語の肝どころ
菊地 康人 『敬語』
3.奈良の都に交わされる声をさぐる
橋本 進吉 『古代国語の音韻に就いて』
4.人生への問いと文章の書き方
里見 弴 『文章の話』
5.切れば血とユーモアの噴き出る文章術
堺 利彦 『文章速達法』
第二章 古典文芸の道しるべ
1.社会人に語りかける古典入門
藤井 貞和 『古典の読み方』
2.古歌を読む分析的知性の強力さ
萩原 朔太郎 『恋愛名歌集』
3.俳句を読み深めることのたのしさ
高浜 虚子 『俳句はかく解しかく味う』
4.現代詩をめぐる「楽しい遍歴」
三好 達治 『詩を読む人のために』
5.読むことのうれしさにみちた近代小説案内
窪田 空穂 『現代文の鑑賞と批評』
第三章 歴史への着地
1.歴史への抑えた怒り
エルンスト・H・ゴンブリッチ 『若い読者のための世界史』
2.歴史的想像力の剣さばき
岡田 英弘 『世界史の誕生 -モンゴルの発展と伝説』
3.ブルジョアの二面性を鮮明に照らす
遅塚 忠躬 『フランス革命 -歴史における劇薬』
4.「記者魂」の躍如としたジャパノロジー
内藤 湖南 『日本文化史研究』
5.歴史の直接的な肌ざわり
中村 稔 『私の昭和史』
第四章 思想史の組み立て
1.世相の向こうに「近代」の醜悪をあばく
金子 光晴 『絶望の精神史』
2.考えるべきことを考えよという指針
田川 建三 『キリスト教思想への招待』
3.思想史からの伝言
岩田 康夫 『ヨーロッパ思想入門』
4.本の「断片」を読みふかめる
内田 義彦 『社会認識の歩み』
5.アラビヤ語とイスラームとの切っても切れぬ関係
井筒 俊彦 『イスラーム生誕』
第五章 美術のインパルス
1.たっぷりとゆたかな「小著」
武者小路 穣 『改訂増補 日本美術史』
2.江戸絵画の見かたをかえる異色の水先案内
辻 惟雄 『奇想の系譜』
3.画家の身にひそむ思想の筋力
菊畑 茂久馬 『絵かきが語る近代美術』
4.「名画」という価値から解放された絵の見かた
若桑 みどり 『イメージを読む』
5.二十世紀絵画に「感覚の実現」を読む
前田 秀樹 『絵画の二十世紀』
私と<狐>と読書生活と -あとがきにかえて
世の職業人でいちばん自由に読書ができるのは、もしかすると、研究者でもなく、評論家でもなく、勤め人かも知れません。
時間は、与えられるものではありません。つくりだすものです。そして、本を読むくらいの時間は、意外につくりだすことができる。
