
引っ越しの力仕事のあと、あっさりした食事が食べたいとのこと。
駅前第3ビルのとまとラーメンが閉まっていて、大丸の天凛豊も貸切で入れず、16階で店を探して、冷麺に落ち着く。
冷麺単品。あっさり味で暑い夏にはぴったりの味。

チーズちぢみをキャンセルして海鮮ちぢみを頼む。
今日から一週間お得な値段(440円)になっている。
具のイカがやわらかくて風味があって、おいしい。これだけでもいいくらい。
また、行きたいね。

梅田散歩
アルベール・カミュ 『シーシュポスの神話』 を読む
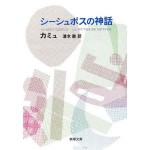
神々がシーシュポスに課した刑罰は、休みなく岩を転がして、ある山の頂まで運び上げるというものであったが、ひとたび山頂まで達すると、岩はそれ自体の重さでいつもころがり落ちてしまうのであった。無益で希望のない労働ほど恐ろしい懲罰はないと神々が考えたのは、たしかにいくらかはもっともなことであった。
神話とは想像力が生命を吹き込むのにふさわしいものだ。このシーシュポスを主人公とする神話についていえば、緊張した身体があらんかぎりの努力を傾けて、巨大な岩を持ち上げ、ころがし、何百回目も、同じ斜面に繰り返してそれを押し上げようとしている姿が描かれているだけだ。ひきつったその顔、頬を岩に圧しあて、粘土に覆われた巨魁を片方の肩でがっしりと受け止め、片足を楔のように送ってその巨魁をささえ、両の腕を伸ばしてふたたび押しはじめる。泥まみれになった両の手のまったく人間的な確実さ、そういう姿が描かれている。天のない空間と深さのない時間とによって測られるこの長い努力のはてに、ついに目的は達せられる。するとシーシュポスは、岩がたちまちのうちに、はるか下のほうの世界へところがり落ちていくのをじっと見つめる。その下のほうの世界から、ふたたび岩を頂上まで押し上げてこなければならぬのだ。かれはふたたび平原へと降りていく。
こうやって麓へ戻っていくあいだ、この休止のあいだのシーシュポスこそ、ぼくの関心をそそる。石とこれほど間近に取組んで苦しんだ顔は、もはやそれ自体が石である!この男が、重い、しかも乱れぬ足どりで、いつ終わりになるかかれ自身ではすこしも知らぬ責苦のほうへとふたたび降りていくのを、ぼくは眼前に想い描く。いわばちょっと息をついているこの時間、かれの不幸と同じく、確実に繰り返し舞い戻ってくるこの時間、これは意識の張りつめた時間だ。かれが山頂をはなれ、神々の洞穴のほうへとすこしずつ降ってゆくこのときの、どの瞬間においても、かれは自分の運命よりたち勝っている。かれは、かれを苦しめるあの岩よりも強いのだ。
この神話が悲劇的であるのは、主人公が意識に目覚めているからだ。こんにちの労働者は、生活の毎日毎日を、同じ仕事に従事している。その運命はシーシュポスに劣らず不条理だ。しかし、かれが悲劇的であるのは、かれが意識的になる稀な瞬間だけだ。ところ、神々のプロレタリアートであるシーシュポスは、無力でしかも反抗するシーシュポスは、自分の悲惨な在り方を、かれは下山のあいだじゅう考えているのだ。かれを苦しめたにちがいない明徹な視力が、同時にかれの勝利を完璧なものたらしめる。侮蔑によって乗り超えられぬ運命はないのである。
このように、下山が苦しみのうちになされる日々もあるが、それが悦びのうちになされることもありうる。悦びという言葉は言いすぎでない。
シーシュポスの沈黙の悦びのいっさいがここにある。かれの運命はかれの手に属しているのだ。かれの岩はかれの持ち物なのだ。同時に、不条理な人間は、自らの責苦を凝視するとき、いっさいの偶像を沈黙させる。突然沈黙に返った宇宙の中で、ささやかな数知れぬ感嘆の声が、大地から湧きあがる。数知れぬ無意識のひそやかな呼びかけ、ありとあらゆる相貌からの招き声、これは勝利にかならずつきまとうその裏の部分、勝利の代償だ。影を生まぬ太陽はないし、夜を知らねばならぬ。不条理な人間は「よろしい」と言う、彼の努力はもはや終わることはないであろう。ひとにはそれぞれの運命があるにしても、人間を超えた宿命などはありはしない、すくなくとも、そういう宿命はたったひとつしかないし、しかもその宿命とは、不可避なもの、しかも軽蔑すべきものだと、不条理な人間は判断している。それ以外については、不条理な人間は、自分こそが自分の日々を支配するものだと知っている。人間が自分の生へと振り向くこの微妙な瞬間に、シーシュポスは、自分の岩のほうへと戻りながら、あの相互につながりのない一連の行動が、彼自身の運命となるのを、かれによって創り出され、かれの記憶のまなざしのもとにひとつに結びつき、やがてはかれの死によって封印されるであろう運命と変わるのを凝視しているのだ。こうして、人間のものはすべて、ひたすら人間を起源とすると確信し、盲目でありながら見ることを欲し、しかもこの夜には終わりがないことを知っているこの男、かれはつねに歩み続ける。岩はまたも転がってゆく。
ぼくはシーシュポスを山の麓にのこそう!ひとはいつも、繰り返し繰り返し、自分の重荷を見出す。しかしシーシュポスは、神々を否定し、岩を持ち上げるより高次の忠実さをひとに教える。かれもまた、すべてよし、と判断しているのだ。このとき以後もはや支配者をもたぬこの宇宙は、かれには不毛だともくだらぬとも思えない。この石の上の結晶のひとうひとつが、夜にみたされたこの山の鉱物質の輝きのひとつひとつが、それだけで、ひとつの世界をかたちづくる。頂上を目がける闘争ただそれだけで、人間の心をみたすのに充分たりるのだ。いまや、シーシュポスは幸福なのだと想わねばならぬ。

扇町通りのダイコクドラッグの先のローソンの手前に、お昼の定食の看板が出ていたので入ってみる。

階段を下りていくとお店がある。
来店がわかるようにチャイムが鳴る。

カウンターとテーブル席のお店。
阿波の鱧料理のポスターが貼ってある。夜は、和食の飲み屋さん。

鯛のあら煮定食(780円)を食べる。
鯛のあら煮、玉子焼き3切れ、ごはん、赤出汁、お漬物。
出汁にまぶして食べる鯛の身はごはんによく合う。玉子焼きもあっさりした出汁巻。あら煮の出汁につけて食べるとちょうどいい味。
ほかには、松花堂弁当やお造り定食などがある。エステサロンと提携しているお店らしく、連れられてくる人もいた。
柳田 邦男 『「人生の答」の出し方』 を読む
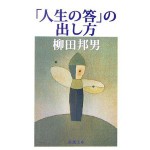
人が生きる時間
人生の「生きられた時間」
私の中に二つの異質な時間が流れていたのだ。一つは、私だけが個人的に直面している現実と結びついた「一人称的な時間」。そして、もう一つは、主観的な感覚や意識に関係なく、誰の上にも共通に流れている客観性を持った「三人称的な時間」である。
人間が生きるうえで決定的に重要なのは、「一人称的な時間」の中で、「生きられた時間」を持てたかどうかということだった。「生きられた時間」とは、哲学者ウジューヌ・ミンコフスキーが提唱した概念だ。
だが、情けないことに、次男が死んで、自分が離人症的な精神状態を経験してはじめて、「生きられた時間」が持てないというのは、ずっと深い実存的な苦しみであったのだと、ようやく実感のレベルで理解できるようになったのだった。
こうして「一人称的な時間」や「生きられた時間」というキーワードを手にしてからは、がんや難病などの厳しい病気と闘いながら懸命に生きている人々に生き方を見る眼をより深めることができるようになったと思う。
最近、がん患者たちがよりよく生き抜くための「生きがい療法」が、少しずつ広まっている。
生きがい療法の基本方針五項目の中で、とくに注目したいのは、次の三つの心得だ。
1)ただ生きようと思うのではなく、自分が自分の主治医になったつもりで、病気をしっかり見つめて、前向きな姿勢で治療を受け、がんと闘っていくこと。
2)今日一日の生きる具体的な目標を自覚して、全力投球すること。
3)人にためになることをすること。
このような闘病の姿勢と生き方を次のように表現することができるだろう。すなわち、進行がんになったからといって、絶望したりうつ的になったりして人生を投げ出すのではなく、あるいはただいたずらに生物的な延命(=三人称的な時間の延命)を求めて医師任せの治療を受けるのではなく、自分が直面している厳しい病気の現実に結びついた大事な日々、つまり「一人称的な時間」を可能な限り密度の濃い「生きられた時間」にするべく、主体性をもって治療に臨み、生きがいを実感できる日々を設計していくならば、納得することのできる「これが私の人生だ(This is my life!)」という物語を書けるに違いない。しかも、そういう生き方を貫くならば、唯々諾々と治療を受けているよりも、結果として、はるかに大きな延命効果を獲得することができるにちがいない-と。
このことは、人生の長さとは何か、ひいては本当の長寿とは何か、という本質的な問題について、一つの答を出していると言えるのではないかと、私はとらえている。
そして、私は、次のようなモデルを考えている。
「人生の長さ(意味のある人生の長さ)」=「生きられた時間の長さ」x「その密度」
ここで一つ、補足しておくべき大事な問題がある。それは、生きがい療法の方針の中にある「人のためになることをする」が、なぜ厳しい病気を背負った自分の生を支えることになるのか、その意味についてだ。
この問題について、最も鋭く明快な解答を出したのは、第二次大戦中のナチス・ドイツの強制収容所で生き残った精神医学者ヴィクトール・E・フランクルだ。飢えと強制労働とガス室による大量殺戮という絶望的な限界状況下で、人格を崩壊させずに生き抜くことができた人々を支えた考え方はどんなものだったのか。フランクルは、『夜と霧』の中で、劇的に気づいたことについて、こう書いている。
<人生から何をわれわれはまだ期待できるのかが問題なのではなくて、むしろ人生が何をわれわれから期待しているかが問題なのである。>
<われわれが人生の意味を問うのではなく、われわれ自身が問われた者として体験されるのである。>
限界状況の中で絶望しないためには、生きる意味についての考え方を180度転換させること、すなわち「人生の問いのコペルニクス的転回」が求められるというのだ。
博報堂ブランドデザイン 沼田 宏充 『あなたイズム ムリなく、自分らしく、でも会社に愛される働き方』 を読む
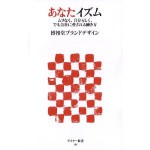
第1章 なぜ仕事は「つまらない」のか
仕事が「つまらない」というのはどういう状況なのだろうか。詳しく分析すると、実は仕事を「つまらない」と感じる要因は、大きく分けて2つある。
ひとつは、その人の「適性」や「志向性」が合っていないこと。
もうひとつは、その人の「スキル」や「才能」が合っていないことだ。
個人の「志向性」が合っていなければ、その仕事も職場もつまらないし、「スキル」や「才能」がフィットしていなければ、結果が出ず、やはりつまらない。「つまらない」は、この2つの要素のいずれか、もしくは両方によって生じていることがほとんどだ。
これは、別の言い方をすると、その人の「持ち味」が活かされなければ、人は仕事や職場を「つまらない」と感じやすい、ということでもある。
だが、このような個人と組織の価値観の接点に着目し、個人の「イズム」を発揮させようと考えている企業はまだまだ少ない。さらに、そのための施策を実践している企業はもっと少ない。
だからこそ、「仕事がつまらない」と感じる人が多いのである。
第2章 自分の「持ち味」、組織の「らしさ」
個人にさまざまな持ち味があるように、組織にもそれぞれの考え方や重視している価値観、固有の雰囲気などがある。私たちはこれを組織の「らしさ」と読んでいる。
個人の持ち味が志向性とスキルに大別でき、それぞれに多彩な要素が含まれているように、組織のらしさもさまざまな要素から構成されている。
たとえば、その組織では、個々人の業績だけを問うのか、それともプロセスの質も問うのか。あるいは、リーダーシップの発揮が良しとされるのか、皆でフラットに助け合うチームプレーが求められるのか。また、個人を尊重したさっぱりとした付き合い方が奨励されているのか、和気あいあいと交流し合う雰囲気なのか....。
「なんとなく働きにくい」「つまらない」「合わない気がする」という場合は、こうした組織のらしさと、自分の持ち味の接点が見つけられていないことが多い。
組織のらしさが分かれば、自分の側から「どこが重なるか」という視点で組織に近づくことができる。
個人の持ち味の円と、組織らしさの円、この2つが重なる部分が双方の接点であり、今後の行動指針になる。
個人と組織のらしさの接点にある価値観を行動指針とすれば、自分の持ち味を活かしながら、組織に貢献するというウィン-ウィンの働き方ができるというわけだ。
この行動指針を、その人らしい働き方をガイドする価値観として「イズム」と定義している。
この「あなたイズム」を発揮することは、すなわち自分の持ち味を発揮することである。それでいて、組織の価値観にも合致する。だからこそ、イズムにのっとって仕事に取り組めば、楽しく働けるうえに、組織にとっても良い影響を及ぼすことができる。