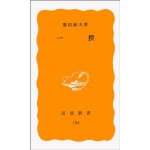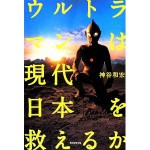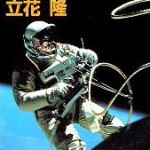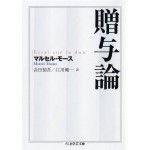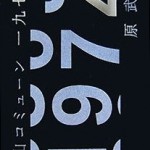森 茂暁 著 『建武政権 後醍醐天皇の時代』 を読む。
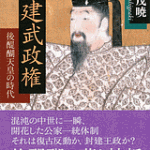
第一章 鎌倉後期の公武交渉
得宗専制の末期症状
約150年間続いた鎌倉幕府の政治過程は、ふつう将軍独裁・執権政治・得宗専制の三段階をもって理解されている。このうち時間的に見て最も長い得宗専制は北条時頼のころに萌芽し、蒙古来襲を乗り切った子時宗の時期にいたって飛躍的な深化をみせ、その子貞時のとき最高潮に達したといわれている。
北条氏の家督を中心に一門、被官といった一部の者たちによって運営された得宗専制の強化は、当然のことながら一般御家人の間に根強い反発・抵抗を増幅させていった。貞時は幕府支配の基礎たる御家人制の疲弊に気付き、金融業者の犠牲のうえに永仁5年(1297)の徳政令を発布し、その再編に最大限の努力を傾けたが、ときすでに遅く、かえって経済界を混乱させるのみであった。
応長元年(1311)の貞時の病死は得宗の支配下に鬱積されたさまざまの矛盾をいっせいに表面化させた。確かな主導者を欠如した幕府内部の権力闘争、寺社統制の失策に伴う宗教界の敵対、悪党の跳梁、いづれも幕府の存立を根底から揺すぶった。逆に後醍醐天皇の側から見れば、倒幕のためのこよなき条件が整うことを意味したのである。
第二章 後醍醐天皇前期親政
1 倒幕運動の展開
後宇多院政の廃止
後宇多上皇が院中に院を聴いたのは二期十年にわたる。
後二条天皇の践祚とともに開始された第一次後宇多院政は、「乾元・嘉元の間(1302~06)、政理乱れず」といわれたように善政の誉れ高かった。その院政が晩節ととのわなくなったきっかけは、まず後宇多上皇の皇后 a遊義門院姈子(後深草皇女)が徳治2年(1307)7月、38歳で没したことである。このとき上皇は出家、大覚寺に入り、法諱を金剛性と称した。皇后の逝去に加えて翌年8月には将来を嘱望した後二条天皇が24歳の若さで早世したのである。たび重なる悲運に遭遇した法皇は政務への意欲を急速に喪失していった。同閏8月3日にはついに所領を第二子中務卿 尊治親王(のちの後醍醐天皇)に譲与してしまう。
尊治親王はこの年の9月19日に立太子、まさに政治舞台への第一歩を踏み出すわけであるが、、同親王登場の背後には父後宇多法皇の意図が大きく働いていた。
こうして世をはかなむ法皇は真言密教へのめり込んでゆく。徳治3年1月、東寺に幸し、前大僧正善助を大阿闍梨として秘密灌頂を受けた法皇は、同2月、西院御影堂において「六箇御願」を立て、東寺を平安初期の姿に復興する事業に、信仰心に裏打ちされた治天下としての全精力を傾けることになる。
法皇には嫡孫をもって皇統を継がしめるという意図があったため、すでに東宮には邦良親王が据えられていた。法皇にとって後醍醐天皇の即位は、邦良親王の成長を待つ間の暫定措置にすぎなかった。(当時の「一代の主」の言葉はそれを象徴する)。しかしこの法皇の宿願は、その崩御と共ともにほぼ反古となる。
室町院領
天皇家の経済は一に皇室領によって支えられた。皇室領荘園は全国に六、七百か所におよんだといれている。そのなかで代表的な大規模荘園群が長講堂領、八条院領、七条院領、室町院領などである。
持明院・大覚寺両統が熾烈な分裂劇を演じた理由の一つに両統の荘園支配に立脚した経済力の均衡性が指摘されている。持明院統は文永4年(1267)に宣陽門院(後白河皇女覲子)から後嵯峨院を経て、180か所におよぶといわれる長講堂領を伝領し、いっぽう大覚寺統は弘安6年(1283)、安嘉門院(後高倉皇女邦子)より百数十か所におよぶといわれる八条院領を手中に入れていたのである。この二つの荘園群はおのおの経済的意味での大黒柱であった。
室町院領といわれる荘園群は、承久の乱後これを獲得した後高倉院から、まず皇女式乾門院利子へ移譲され、さらに利子はこれを宝治元年(1247)、猶子にむかえた中書王宗尊に伝えようとしていた。
式乾門院は、建長3年(1251)に没するが、その2年前の建長元年、処分状をしたためておいた。それによって、件の荘園群は一期ののちは、宗尊に譲るという条件付きで姪の室町院に伝えられることとなった。この宗尊とは後嵯峨院の皇子で、鎌倉幕府の執権北条時頼の要請によって、建長4年(1251)、11歳ではじめての皇族将軍として東下した、かの宗尊親王のことである。
将軍宗尊はやがて得宗北条時宗との間に摩擦をひきおこし、文永3年(1266)7月、将軍の地位を子惟康王(3歳)に譲り、15年間におよぶ鎌倉生活を終え帰京することになる。問題の荘園群は予定通り宗尊に移譲されるかにみえた。ところが、当の宗尊は文永11年(1274)、33歳で没したのである。このため、せっかくの式乾門院の遺志は実現されぬまま消滅した。一期分としてこれを預かった室町院も正安2年(1300)5月、73歳で没したが、彼女がこの荘園群に対する措置をまったくとらなかったことが、紛争の種をまくことになった。のちに争奪の対象となるこの荘園群を室町院領という。
正安3年1月、後二条天皇の践祚に伴い、父後宇多上皇の院政が開始される。室町院領はごく自然のなりゆきとして宗尊の娘瑞子(土御門姫君)に帰した。ところが翌年、瑞子は准三后に列せられ、永嘉門院という院号をたまわり、後宇多上皇の猶子となる。この措置は女院の伝領する室町院領を目当てにした策略だと考えられている。むろん、持明院側は強硬に異議を申し立てた。そして結局、幕府の調停によって正安4年8月、室町院領は両統に折半された。このとき大覚寺統は二十余カ国にわたる53荘郷を獲得した。
室町院領をめぐる大覚寺側の攻撃は、文保の和談をたてに花園天皇を退位させて登場する後醍醐天皇の治世となって以降、再燃する。
両統の争いは持明院側から関東に愁訴された。このとき幕府が正安4年の折半決定を支持したため、天皇自身これ以上の介入を断念せざるを得なかった。
無礼講
正中の謀議は無礼講(あるいは破仏講)と称された乱痴気パーティーのなかで準備された。
およそ近日或る人云く、(日野)資朝、俊基等結衆会合し乱遊す。或いは衣冠を着せず、ほとんど裸形にして、飲茶の会これあり。これ達士の風を学ぶか。(中略)この衆数輩あり。世にこれを無礼講の衆と称すと云々。(花園天皇宸記)
正中の変
元亨4年(正中元)9月23日の北野祭を期したクーデター計画の概要は次のようである。北野祭では例年喧嘩がつきもので、その鎮定には六波羅探題の武士が出動する。このすきをとらえて北方探題 北条範貞を誅殺する。南都の衆徒は交通の要衝、宇治と勢多を固める。これら一連の指揮は資朝・俊基が行い、近国武士を多く味方に引き入れる。
しかし、この企ては一味同心したはずの土岐頼員の密告によって水泡に帰してしまう。頼員は同族の多治見国長を通して、資朝の奉じた後醍醐天皇の綸旨に接したのであったが、ことが成就しそうになく、関東の恩にも背くわけにはいかないので、妻の父である六波羅奉行人斎藤俊行にいっさいをばらしてしまったのである。
後醍醐天皇はこの事件との係累を否定した。事前には「関東執政しかるべからず、また運すでに衰ふるに似たり。朝威はなはだ盛んなり。あに敵すべけんや。よって誅さるべし」と語気強く倒幕意志をあらわにしていた天皇が、一転して「主上すこぶる迷惑し給う」と態度を変えたのである。
洛中の支配
荘園制の体制的発展が「王侯の宿営地」としての古代都市京都を政治・商業の中心都市=中世都市へと転換させたのは平安時代の後期院政期とみなされている。商品流通・貨幣経済の中心的地位を獲得し、公家をはじめ寺社権門を集住させた京都を王土思想をもとに掌握することは、後醍醐親政にとって喫緊の大問題であったと言える。
後醍醐天皇は親政開始と同時に、きわめて厳しい専制的姿勢でこの課題(洛中の土地を人の支配)に着手した。元亨2年(1322)に発せられた神人公事停止令・洛中酒鑪役賦課令は親政全般を貫く基本法令として注目される。
前者は洛中を中心に集住する寺社権門に属して、幅広い商業活動をおこなってきた神人の本所に対する諸公事を免除するというもの、後者はこれまた諸自社の神人として交易にたずさわっていた洛中の酒屋を、内廷経済の基盤として再編しようとしたものである。
この二法令の眼目は洛中神人に対する寺社権門の本所支配権を断ち切り、彼らを天皇の供御人として編成することにあった。
以上の神人に焦点をあてた施策が「人」に対する支配とみれば、いまいっぽうの「土地」に対するそれは地口銭の賦課に求められる。
地口銭とは朝廷・幕府などの公権力が、洛中の商工業者に対し地口、つまり道路に面した部分の長さに準拠して尺別に賦課した臨時課税である。この課税は商業都市としての洛中の特質にもとずくものである。
第三章 建武政権の成立と展開
2 新政の諸相
新政の理念
元弘3年6月5日、二条富小路内裏に還幸した後醍醐天皇は「自立登極」し、重祚の礼におよばなかった。2年前皇居から脱出した天皇にとって以降の幽囚の日々はあくまでも遷幸にすぎなかったのである。偽朝たる光厳朝下の任官・叙位は停廃されねばならず、もとのメンバーが次々と復官した。
帰京後、天皇がみせた政務に対する意欲にはすさまじいものがある。『梅松論』にみえる「古の興廃を改て、今の例は昔の新儀なり。朕が新儀は未来の先例たるべし」という一文は新政の基本理念を端的に表現している。新しい政治が「延喜・天暦のむかしに立帰」ったと描かれるのもいわれなきことではない。後醍醐天皇の新政府の真面目は、徹底的な天皇親政のしくみを採用したことにある。このため院政はしかれず、摂関・太政大臣もおかれなかった。
後醍醐天皇は政務を担当するにあたり、まず記録所、ついで恩賞方・雑訴決断所などの官衙を開設し、親政体制を支える機構をととのえる。
天皇に課された最大の難問は、公武両社会をいかに統一的に支配するかであった。官制の特質も究極的にはここに帰着する。