原 武史著 『滝山コミューン一九七四』 を読む。
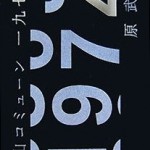
1 序
私が小学6年生になった1974年、七小を舞台に、全共闘世代の教員と滝山団地に住む児童、そして七小の改革に立ち上がったその母親たちを主な主人公とする、一つの地域共同体が形成された。たしかにごく一時的な現象ではあったけれども、「政治の季節」は、舞台を都心や周辺部の山荘から郊外の団地への移しながら、72年以降もなお続いていたと見ることもできるのである。
私はここで、国家権力からの自立と、児童を主権者とする民主的な学園の確率を目指した地域共同体を、いささかの思い入れを込めて「滝山コミューン」と呼ぶことにする。
倫理学者の古茂田 宏は、戦後教育の三つの潮流について触れた「文化と文化の衝突」(『講座学校第3巻 変容する社会と学校』、柏書房、1996年所収)と題する論文で、戦後第一段階に当たる1970年頃までの学校教育に対するまなざしに見られた「美しい物語」につき、次のように述べている。
国家主義的な滅私奉公を要求する非合理な道徳教育の押し付けではなく、一人一人の子供たちを賢く幸せにするための科学教育を・・・・といったスローガンの中には、子供の自然な発達段階に応じた(押しつけでない)真理の教授と民主的社会の形成とが予定調和するという美しい夢が託されていた。
「日の丸・君が代・特設道徳」といった上からの押し付けに対して子供を守るスタンスから抵抗した民主教師たちの中には、自ら教育行為そのものが別な形での権威主義-客観的知の権威主義(中西新太郎)-をはらむことになるなどという自覚はなかったし、またそういう自覚が促される歴史段階でもなかった。
教育とは人類の自己形成の営みであり、学校はこれを共同的に具現する場所などだという美しい物語が一定のリアリティをもって維持されたのである。
古茂田によれば、1970年頃を境に見られる第二段階になると、戦後民主主義教育のオプティミズムが維持できなくなり、校内暴力、イジメ、登校拒否などの事態が次々に起こって学校的秩序が解体していく。
「滝山コミューン」とは、「美しい物語」がまだリアリティをもっていた時代の最後に現れたものちいってよかった。実際に当時、文部省大臣官房統計課が毎年発表していた『学校基本調査報告書』によれば、「学校ぎらい」を理由とする全国の小学生の長期欠席者数(50日以上の欠席者数)、つまり登校拒否児童の数は、奇しくも「滝山コミューン」が確立された74年に最も少なくなっている。
いまでこそ、学校が本質的に権力性をもつというのは教育学で自明の前提となっているが、当時はそうではなかった。七小の教師たちは、「自らの教育行為そのものが別な形での権威主義をはらむことになるなどという自覚」はつゆほどもなく、コミューンの理想を信じ、その建設に向かっていったのである。
3 「水道方式」 と 「学級集団づくり」
全国生活指導研究協議会、略して全生研は59年、日教組教研第八次大阪集会で生まれた民間教育研究団体である。「日教組の自主教研の中から誕生した民間教育研究団体であるという点に、他の民間教育研究団体と異なる特色をもつ」という。
そこには一見、憲法や教育基本法に保障された「個性の尊重」が「内外の反動的諸勢力」によって脅かされているという、典型的な護憲派リベラルの主張が読み取れる。
だが、全生研で強調されたのは、集団主義教育であった。「大衆社会状況の中で子どもたちの中で生まれている個人主義、自由主義意識を集団主義的なものへ変革する」という文面からは、世界が東西の二大陣営に対立していた時代にあって、まだ理想の輝きを失っていなかった社会主義からの影響が濃厚にうかがえる。「個人」や「自由」は、「集団」の前に否定されるのである。
このような集団主義教育は、旧ソ連の教育学者、A・S・マカレンコ(1888~1939)の著作によるところが大きかった。
全国組織に並行して、地方の支部もつくられていった。63年には、全生研の教育包方針をまとめた『学級集団づくり入門』が明治図書出版から刊行され、71年には第2版が刊行された。
全生研によれば、集団とは「物理的な ちから としての存在」である。「集団はひとつのちからになりきらなければ、社会的諸関係をきりひいていき、変更していくことは不可能である。
まして、非民主的な力に対抗していくためには、集団はみずからを民主的なちからに高めるほかはないのである。」集団は、「民主的集団」、つまり「民主集中制を組織原則とし、単一の目的に向かって統一的に行動する自治的集団」にならなければならない。そのためには、目的自覚的な教師の指導が不可欠であるが、「集団を民主的なものにするのはあくまでも集団自身であり、子どもたちである」。児童は教師から「正しい指導」を受ければ、必ず集団の担い手としての自覚をもち、自ら集団を変えていくとされるのである。
「学級集団づくり」には、「よりあい的段階」「前期的段階」「後期的段階」という三つの発展段階がある。「学級集団はこのような三つの発展段階をたどりながら、その合目的的な発展の法則性を展開していくのである」。ただし実際には、「後期的段階」の実現は「まだかなりむずかしい」とされる。
全生研の唱える「学校集団づくり」は、最終的にその学級が所属する小学校の児童全体を、ひいてはその小学校が位置する地域住民全体を「民主的集団」に変革するところまで射程に入っていたのである。
「滝山コミューン」の思想的母胎がここにあった。
しかも滝山団地にはコミュニティセンターがなく、自治会も割れたいたのに対して、七小は1街区から3街区まですべての児童が通学していたから、小学校こそコミュニティの中核としての役割を果たしていた。七小が「滝山コミューン」の舞台となる条件はそろっていたのである。
さらに目を外に転じれば、全生研が影響を受けた旧ソ連の集団主義教育は、団地を中心とするソビエト社会の中で発展したものであった。
