竹下 節子 著 『キリスト教の真実』 を読む
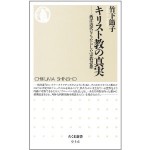
第二章 暗黒の中世の嘘
新しい思想は古い思想を仮想的としてみずからの正統性を主張する
近代の成立において、主としてプロテスタント勢力がローマ・カトリック教会を「敵」と見なし、その地位を貶めることによって自らの正統性を証明しようとした。
知を共有財とみなすキリスト教の教育
シャルルマーニュは、「知性」の必要性は、エリートだけでなく、庶民にも求めらるべきとだとして、「無償の学校」制度を設けた。
学校制度が可能になったのは、各地で「蛮族」の襲撃を逃れた多種多様の書物が、あらゆる教会堂や修道院へすでに避難させられていたからである。600年から750年の間にフランク王国内だけでも200の僧院が建てられた。シャルルマーニュの誕生からその孫の死までの期間(768-855)には、27の司教座聖堂(カテドラル)が建ち、417の修道院が建設された。偶像崇拝禁止であったが、読み書きできない民を教化するために、カテドラルや修道院は新旧聖書の図像で豊かに飾られた。
これら「知の流通」は、キリスト教の普遍主義に支えられていた。キリスト教においては、知は個人財産とみなされず、修道院図書館などに保存され、書写によって複本がつくられ、古典学術が継承されていった。背景には、キリスト教には全ての人間の自由意志を前提とした教育理念が備わっていたことがある。
修道院に付属学校が開設された後に、司教区の学校が作られる。司教区学校は聖職者養成のためだけにできたのではない。学校に集った若者にはラテン語の基礎や教養科目が教えられ、古典学術を継承するために不可欠な素養を身につけさせた。カリキュラムは、文法、修辞、弁証(論理)の三学と算術、幾何、天文、音楽の四科から成り立っていた。一方で神学の教育は聖職者の身分を擁する者のみに与えられていた。
大学の誕生
大学(ユニヴァーシティ)は、カトリック教会がヨーロッパ中に設置した教育研究機関だった。ユニヴァーシティの語源は、普遍=カトリックと同じものだ。教会という言葉が「教会堂」の建物を表すのではなく聖職者と信者の集まりを意味していたように、ユニヴァーシティも、教授と学生の共同体を意味するものであり、講義はカテドラル(司教座のある教会)の内部や私邸の中で行われていた。ローマ教皇はこのユニヴァーシティの監督保護者であり、教授に対する支払いが滞るなどの苦情が教皇にまで持ち込まれて処理されていた。
大学の誘致は経済効果があるため歓迎されていたが、学生を含めた大学関係者は消費者として地域経済に貢献するが、定住の意思を持たない「よそ者」であり、生産者でない。彼らは対等な市民とはみなされず、住居、食物、書物などの売買で騙され、警官からは暴力をふるわれた。そのような敵意から大学を保護するために、ローマ教会はかれらに「聖職者(clericus)」の身分を付与した。「聖職者に対する暴力」は、世俗でも犯罪とされ、聖職者自身は原則として教会の法廷によってのみ裁かれる地位を与えられた。この「大学」のおかげで、聖職者=知識人という構図がかたちつくられるようになった。
当時の大学は、14歳からの中等教育も受け持ち、庶民家庭の子弟が少なくなかった。三学四科の教養科目(リベラル・アーツ)と哲学(リベラル・アーツを統合して神学の予備となる高度な論理的思考だった)を修めた後で、さらに法学(世俗法と教会法)、自然哲学(自然科学)、医学、神学を学ぶことが可能だった。ラテン語で出回るようになったユークリッド幾何学、アリストテレスの哲学や自然学、ガレノスの医学書などが教科書として使われた。
ユニヴァーシティにおける教育機関はスコラ(scolas)であり、そこでの教育がスコラ学という方法論になった。社会の変化に応じて学問の方法が大きく変わっていった。教師たちは単に古典の購読だけでは満足できなくなり、理性を重視し、主論と反論を戦わせて結論を導く弁証法的な主知主義を用いて深い意味を汲もうとした。まず問いがたてられ、互いに反する仮説が提示され双方の議論の妥当性を検討し、自分の結論を提示したうえで、反論に答えるという形式が、次第に確立していった。スコラ学の誕生である。
第三章 「政教分離」と「市民社会」と2つの型
カトリックとプロテスタントの棲み分けは、次のようにおこなわれた。
ローマ・カトリックのホームグラウンドであるイタリアは、カトリックのまま。イベリア藩半島も15世紀末に達成されたレコンキスタによってカトリック陣営が強力だったため、カトリック圏にとどまった。10世紀以来神聖ローマ帝国皇帝を選挙で選んできたオーストリアからドイツ、中欧に及ぶ地域は、ハプスブルグ家がカトリックを維持し、他の領邦国家は、カトリック公とプロテスタント公に分かれた。1648年のウェストファリア条約以来、各国の領主が帰依した宗派が国の宗教となり、他の宗派の信者たちは、改宗か移住をすることで棲み分けを維持した。
絶対王権下にあったイギリスとフランスでは、どちらの王も宗教的権威のトップに立つカトリック教会と拮抗しようとしてきた。ヨーロッパ中をネットワーク化している教区と司教区と修道会を束ねるローマ教皇に対抗するには、主に3つの方法が考えられる。
①国内の司教や司教区や修道会長の任命権を獲得して血縁者に委任する。
②ローマ教会と断絶して国内のインフラをそのまま流用して王が「国教会」の長となる
③教会の財産を没収して市民宗教を作る。
フランスは最初の方法を選んだ。つまり、司教の任命権を得ることでガリア教会の自律性を確保しようとした。
イギリスは2番目の方法を選んだ。ローマ教皇に破門されて国教会を興した。
すなわち、フランスのおける政教分離は、それまでカトリック教会が一手に担っていたネットワークや社会運動から宗教のレッテルを外し、それらを政府がそのまま継承し、カトリック教会が独占していた利権システムを解消または吸収したものになった。
そのおかげで、フランスの政教分離は、「横割り二層型」になった。すなわち、「公共空間」における「宗教のレッテル外し」を各宗教が認め、宗教行為(あるいは宗教否定行為)と宗教的な信条はともに「私的空間」に追いやられたわけである。このことこそが、共和国主義の「普遍性」の本質である。たとえ「私的空間」であったとしても、その空間が異なる信条を持つ人びとからなる共同体に属しているのであれば、個人的な信条にもとづいたふるまいをすることは許されない。共同体のマジョリティが多数の力でみずからの主義をマイノリティに押し付けることは禁止され、もしそのような事態が生じた場合には、国家が「共和国主義」の普遍理念の名のもとに介入できるという伝統がある。
「民主主義」の概念には「多数決」に従う、というものがあるが、フランスを含めた、「カトリック否定型」の近代を作ってきた国の大きな特徴は、「多数決」よりも「普遍理念」が優先される普遍主義にある。
アメリカという国家は、ヨーロッパでマジョリティをしめるカトリック国家や、そのヴァリエーションとして国教会を持つイギリスを比べると明らかに異質である。
イギリス国教会から迫害されたマイノリティであるピューリタンの男たちによって「開拓」された「新天地」であり、既成の利権システムなどは存在しない世界だった。建国の核となったのは、WASPと呼ばれる白人アングロサクソン・プロテスタントという宗教的なレッテルに強固に結びついた同質の共同体だ。
アメリカのアイデンティティの核は、WASPのそれである。アメリカは「神の国」であり、アメリカの社会でリーダーシップをとるには、「アメリカの神」を掲げ、神の名によってアメリカを祝福することである。アメリカでは、政教分離を「縦割り」にして、宗教は公生活の「両輪」に一つとなる。政治家が所属教会を明らかにし、日曜日のミサに出ることは社会性と道徳性の証明にもなっている。
フランスの民主主義
フランスのおいて、民主主義はフランスの死守する「共和国主義」を担保するツールの一つである。アメリカにおいては、民主主義は功利主義経済システムを担保する「建前」である。フランスの共和国主義とは、出身地や人種や宗教の違いにかかわらず、同じ国に住む人間が、「自由・平等・博愛」という同じ共和国原理を共有し、それを、個人のアイデンティティのうちに理性的に「統合」していくことを目標にしている。
子どもたちはそれぞれの家族や共同体の文化や宗教の影響を受けて育っているが、その偶然の「与件」の特殊性の外側に、「普遍価値」があることが教えられ、普遍性という物差しを基準にして考える思考訓練がなされる。自分の頭で、自分の「与件」について考え、判断するならば、それをリセットして、共同体の価値観や伝統や習慣や文化や宗教を離脱して別のものを選択する自由が存在することを気づかせることが可能である。これが共和国の公教育理念である。
アメリカの民主主義
アメリカの教育の場において最も重要視されているのは、労働市場に見合った生産者、即戦力になる人間を養成することである。アメリカの教育において、「実学」とは別の「道徳」や「倫理」はどこで教えられているかというと、子供たちの生まれて育つ共同体であり、宗教行事の場である。アメリカにおいて「普遍的」なものは、経済活動における数の原理であり、競争原理である。「道徳」や「文化」や「価値観」については、特殊であっても「共同体的」であっても一向に構わない。いやむしろ、「道徳観」を持つ証明、「良心の査証」として、何らかの「宗教」への所属は大切な要素である。教育の場には「民主主義」の言葉と「星条旗」があればいい。
アメリカの政教分離は、功利主義経済を担保する宗教と、それを容認する政治という両輪なのだ。
