今尾 恵介 『地図で読む戦争の時代 描かれた日本描かれなかった日本』 を読む
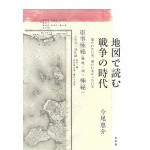
はじめに
地形図を作り始めたのは、どの国でもたいてい陸軍である。もちろん海図は海軍が作った。陸であれ海であれ、国を守るためには正確な地図が必要であることは当然である。しかし一方で、他国を侵略するにも、先立つものは地図であった。たとえば日本の地形図の作成は昭和十二年に日中戦争あたりから目に見えて「外地」の地図作りの比重が激増し、「内地」の修正作業はまったく滞ってしまった。中国内陸部からインド、東南アジアから南太平洋まで、兵站線の拡大の前触れのように、測量戦線も拡大していったのである。
戦時体制下では、安全保障上重要な地図の取り扱いは厳重を極めた。「軍事極秘」の記載のある地形図は軍港都市・呉にほど近い要塞地帯のもので、軍や政府関係のごく限られた人しか目にする機会はなかったはずである。このような地域の地形図はもちろん一般人が入手することは不可能で、カタログである地形図一覧図でもその部分だけ空白になっていた。裏面には識別番号が捺印されているこんな地形図を戦争中に他人に譲り渡すことなど考えられないが、60年以上の歳月を経て、おそらく関係者の遺族が古書市場に流通させたのだろう。それをたまたま私が入手した。
本書のテーマは、2つある。
- 地図で戦争の時代を読む
- 戦争の時代の地図を読む
前者は日本の近代化以降にたどってきた軌跡、すなわち他国を侵略して植民地を経営し、また空襲を受け、連合軍によって占領された時代を、地図を通して観察することである。戦前には植民地化された土地にしばしば日本風の地名が付けられたが、当然ながらその土地を測量したのは日本政府の機関であり、もちろん日本語の凡例のついた地形図上の印刷された。やがて戦争も日本の旗色が悪くなり、本土がたびたび空襲される事態を迎えるが、敗戦を迎えたこの国の地形図作成スタッフに、黒々と描かれていた密集市街地 を白く疎らな、焼け残った建物だけを表示した閑散たる絵柄に変貌させた。内心の無念はいかばかりだったろう。連合軍はその空き地の上に有無を言わさず自ら の施設を作る。
後者のテーマは、戦争の時代にどのように地図が情報統制され、作成者の意図でいかに歪められたか、地図そのものを観察するものである。公開するにふさわしくない場所は図上で広大な空白とし、さらに時代が進むと軍事施設を住宅地と偽って表現するなど虚構が描かれた。敵の目を欺くためとして、結果的に多くの国民の目を欺いたのである。それどころか、その偽りを見抜く術を知らなければ、後世に生きる現代人でさえ引き続き欺き続ける厄介な存在になった。
地図を通して、「戦争の時代」を俯瞰してみると、実にいろいろなものが見えてくる。
焼け跡に出現した飛行場
市街地->焼け跡->公園
「水の都」だった大阪は大幅な変貌を余儀なくされた。西横堀川の西側がいわゆる西船場であるが、現在ここには9.7ヘクタールに及ぶ広い靭公園がある。
この場所はかつて雑喉場(ざこば)と呼ばれ、一帯には江戸初期から塩干魚や鰹節、それに干鰯を扱う問屋が軒を連ねていた。干鰯とは文字通り干して固めたイワシであるが、食品ではなく肥料である。これを畑に入れると綿が良く育ち、全国に知られた河内木綿は北前船で全国に運ばれた。時代を経ると九十九里浜も干鰯の産地となった。九十九里浜名物の地引網も、元は紀州の漁師が伝えたのだという。いずれにせよ、イワシは「繊維工業の原料」だったのである。
その靭一帯は昭和20年(1945)の米軍機の空襲で灰燼に帰してしまったが、広大な焼け跡を連合軍が接収し、小型軍用機を発着させるための飛行場を造成した。しかし占領が終わった昭和27年(1952)6月に接収は解除となり、公園として生まれ変わることとなった。
靭公園には、次のように記された石碑がある。
「この公園の整地は飛行場あとを昭和二十七年度から昭和三○年度の失業対策事業により行われたたものである。 大阪市」
