畑村 洋太郎 著 『決定版 失敗学の法則』を読む
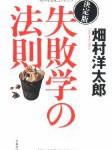
第1章 失敗学の基礎知識
①逆演算で失敗の「からくり」がわかる
目に見えている「結果」から、まだ見えていない「原因」に辿っていくことを失敗学では、「逆演算」と呼びます。失敗学では、「原因」を「要因」と「からくり」の2つに分けて考える。つまり、失敗の構造を「要因」「からくり」「結果」の三要素から構成されていると考える。失敗学における逆演算を正確に記せば、「結果」から「要因」と「からくり」という見えない二つのものを逆に辿って探していくということになる。
(第一段階) 分解
失敗の「原因」をしるために「からくり」と「要因」に分けて考える。
(第二段階) 逆算
「からくり」の正体を知るには「からくり」の構造を仮設する。逆演算の考えを入れ、出力から入力を逆算する。
(第三段階) 推測
「からくり」に架空の「要因」を入れてみて、架空の「結果」を推測する。(第四段階) 一般化
「要因」「からくり」「結果」の関係を一般化し、予測・類推につなげる。
②「失敗の脈絡」分析で失敗を予測
逆演算によって一般化した失敗の「要因」「からくり」「結果」の関係のことを失敗学では「失敗の脈絡」と呼ぶ。「失敗の脈絡」を使って類推すれば、別の分野でも、どんな失敗がどういう経緯で起こるかを予測することができる。
③失敗は確率現象
労働災害の発生確率に関する法則に『ハインリッヒの法則』がある。
一件の重大災害の裏には二十九のかすり傷ていどの軽微な災害があって、さらにその後ろには、ヒヤリとしたりハッとして冷や汗が流れるような事例が三百件潜んでいるというものである。
失敗についても、ハインリッヒの法則と同じことがいえる。同じ要因があっても致命的な大失敗が起こる確率は三百三十分の一であり、軽度の失敗が起こる確率は三百分の二十九で、残りの「ヒヤリ」体験は、実際にはたいした失敗にはつながりません。重大災害は、三百分の一という極めて低い確率で起こる確率現象なのです。
④失敗は拡大再生産される
同じ「失敗の脈絡」で失敗が繰り返されると、させん状に悪循環を起こし、その打撃はどんどん深刻化していく。これを「失敗の拡大再生産」と呼ぶ。
⑤千三つの法則
日本には昔から”千三つ”という言葉があって、「何かの賭けをしたとき、うまくいくのは千に三つぐらいしかない」という意味で使われてきたが、新たに挑戦したことが成功する確率もまさに”千三つ”です。
ゼロから新規事業をスタートさせるにあたり、少なくとも10個くらいの要素(企画内容、技術、事業を興す本人の資質、資金、設備、場所、人材、流行、社会の経済状況、人脈)がすべてうまくいって初めて、事業が成功する。事業の成功には、成功率2分の1の要素が10個必要だとするとその成功率は、2分の1の10乗、つまり1024分の1になる。
⑥「課題設定」がすべての始まり
無駄な失敗を防ぎ、新たな創造の種を生み出すために、まず最初にすべきことは、自分自身の中に課題(問題意識という言葉でも置き換えられます)を持つことです。
課題とはすなわち、「自分はいま何をすべきか」という、行動を起こすときのテーマです。そして、それを解決する方法を考える。この「課題設定」こそが、失敗に直面したときの判断力を、そして新たなチャレンジをしようというときの企画力を鍛えるのです。
「課題設定」のコツは、なにかひとつの事件や事象をよく観察することでうs。そして、そこにはどんな問題が起きていて、それに対して自分は何をしたらいいかを考える。そのひとつひとつが課題なのです。
⑦「仮想演習」がすべてを決める
新たな創造のための第一歩である「課題設定」が済めば、その後は「仮想演習」でその課題をいかに解決すればいいのかを思考することが重要です。他の誰かがやっていることを観察したり、頭の中で「あの場合はこうすればいい」「あの場合はこうすべきだ」などと考えながら、起こりうる失敗を想定していると、いろいろなことが見えてきます。
この「仮想演習」は、失敗学においてかなり重要な意味を持っています。
第2章 失敗の理解の不可欠な知識
⑧暗黙知を生かす
何かひとつのことを行うとき、その分野に関わっている人なら誰もが必ず考えていること、無意識での着眼点というものがある。そして、そこから失敗を防ぐための、あるいは成功につながるいろいろな原理を導き出します。それらはあえて文章に書かれることもなく、多くの場合は言葉にして伝えられることもありません。しかし、それらはその分野に関わっている、誰の頭のなかにも厳然として存在している、いわば「暗黙知」なのです。
とくに失敗に関する「暗黙知」は、あからさまにわかるような形にすること、つまり「形式知」に変えることがとても重要です。というのも、失敗に関する情報はいつも隠れやすくなかなか表に出ないという性質がありますし、時間が経ってしまったり、人から人へと伝えられていく間に、消えてなくなってしまうからです。したがって、失敗の暗黙知を見つけたら、積極的に文章や図式、数値などにして形式知に変え、記録することが重要です。
⑨質的変化を見落とさない
ある産業が急激に成長したり、ある会社が莫大な利益を上げるようになったとき、その量的変化がどういう意味を持っているのかを客観的に考え、同じものを生産し続けるのがよいのか、転換期はいつなのかを判断して、組織や運営方法の構造を改善していかねば、その産業や会社は膨張を続け空中分解を起こし、壊滅的な打撃を受けることになる。
⑩チャンピオンデータは闇夜の灯台
「チャンピオンデータ」とは、「どうやったのかはわからないが、とにかくすでに他の人がその目標を達成している状態」のことで、闇夜を灯り無しで歩くような創造の仕事においては、彼方に見える灯台のような希望の光になるのです。
⑪「山勘」は経験のエッセンス
「暗黙知」とともに失敗を防ぐ大きな力となるのが「山勘」です。
山勘というのは、もはや「知」でもなく、その日地がやってきたすべての経験や行動の結果体得した、状況さえ入れれば答えが直接出てくるような超高速の判断回路のことなのです。
⑫すべてのエラーはヒューマンエラーである
人間のやることに「完璧」はない。人間の動くところには必ず失敗が起こる。これは、失敗学の根本的な考え方です。
⑬新規事業は隣接分野でしか成功しない
新たな分野というのはとても魅力的に見えます。それが将来的に伸びる可能性を持っていたらなおさら、飛びつきたくなるでしょう。そして、新たな挑戦をするには企業風土を変える必要があります。しかし、実際には企業風土を変えるのは至難の業です。しかも、飛び込んだ場所には既存の勢力がいる。そんなところで成功するのは、ほとんど無理です。
