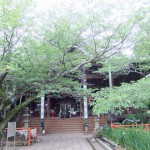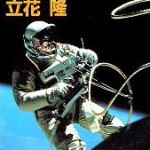マルセル・モース 著 『贈与論』 を読む。
 贈与論
贈与論
第4章 結論
1 道徳的な結論
われわれの道徳や生活の大部分は、いつでも義務と自由とが入り混じった贈与の雰囲気そのものの中に留まっている。幸運にも今はまだ、すべてが売買という観点から評価されるわけではない。金銭面での価値しか持たない物も存在するが、物には金銭的価値に加えて感情的価値がある。われわれは商業上の道徳だけをもっているわけではないのである。いまだ過去の風俗を持ち続けている人々や階級が残っているし、われわれの殆どは一年のある時期もしくはある機会に過去の慣習に従う。
返礼なき贈与はそれを受け取った者を貶める。お返しするつもりのないのに受け取った場合はなおのことである。
喜捨はそれを受ける者の感情をいっそう害する。したがって、われわれの道徳は、裕福な「施し好き」による無自覚で無礼な慈善を無くそうと最大限の努力を払うのである。
「礼儀」として、招待にはお返しをしなければならない。ここに古い伝統的基盤の痕跡と古い貴族的なポトラッチの痕跡がみられる。また、人間の活動の根源的な契機、すなわち同性間の競争心、男性の持つ「生来の支配的傾向」が浮かび上がっているのがみてとれる。そこの表れているのは、一方では社会的基盤、他方では本能的基盤、そして心理的基盤である。われわれの社会生活のような特殊な生活においては、われわれのあいだで今も言われているように「借りをそのままにしておくことができない」。われわれは貰ったより多くを返さなければならないのである。「人におごること」は常に、より豪勢に、よりたくさん行われる。そうゆうわけで、われわれが幼い頃のロレーヌ地方では、普段は慎ましく切り詰めた生活を生活を送っている村の家族が、守護聖人の祝日、婚礼、聖餐式もしくは葬儀などに際し、接待のために破産することまであった。このようなときには「大富豪」ぶらなければならない。われわれの国民の一部はいつもこのように行動し、来客、祝祭、「心付け」に関しては、むやみに金を使うとさえ言えるかもしれない。
招待は行われなければならないし、招待には応じなければならない。このような慣習をわれわれは自由主義的な組合の中でさえも保持している。
誰かが欠席することはまさに凶兆で、妬みや「呪い」の前ぶれ、証であるとされたのである。村人すべてが儀式に参加するというような地方が、フランスにはまだ多く存在する。プロヴァンス地方では子供が生まれると、人々は卵その他の象徴的な贈り物を持参する。
売却された物は依然として霊魂を持っている。かつての所有者は売却した物の後を追い、物の方もかつての所有者のもとに戻ろうとする。
クランからクランへ全体的給付体系とわれわれが呼ぼうとするもの-つまり個人と集団が互いにすべてのものを交換する体系-は、われわれが確認し理解しうる限りにおいて、経済と法の最も古い体系を作っている。それは贈与=交換の道徳が浮かび上がったその背景を形作っているものである。さて、このような体系は、大小の差はあれ、われわれが望む社会のあり方とまさに同じタイプのものである。
つまり、利己を脱却し、自発的にそして義務的に贈り物をすること。これに間違いない。マオリ族の優れた格言もそれを述べている。
「貰ったのと同じだけ施しなさい。そうすれば万事うまくいく」。
2 経済社会学上および政治経済学上の結論
贈与=交換の経済全体は、いわゆる自然経済や功利主義的経済の枠組みからほど遠いことを、われわれな何度も繰り返してきた。
「未開」社会においても価値概念は機能している。このことについて述べるなら、そこでは膨大な剰余が蓄積されるのである。それらは大抵、相対的に巨額な奢侈を伴う全くの浪費に充てられるが、金儲け主義な面はみられない。富のしるしや一種の貨幣も存在し、これらも交換される。しかしこの豊かな経済全体はなおも宗教的要素に満ちている。すなわち、貨幣はまだ呪術的力を持ち、クランや個人と結びついている。各種の経済的活動、例えば市のようなものには儀礼と神話が浸透している。各種の活動は儀式的、義務的そして実効的性格を持ち続けている。つまり儀礼と法で満たされている。
貨幣の使用はその他の省察のヒントとなるだろう。
トロブリアンドのヴァイグアすなわち腕輪と首飾りは、アメリカ北西部の銅製品やイロコイ族のワムパンとまったく同じように、富そのものであると同時に富のしるしであり、交換や支払いの手段であり、人に与えるか、さもなくば破壊しなければならない物である。ただし、ヴァイグアはそれを用いる者に結びついた担保であり、この担保はその者を拘束する。しかし他方では、ヴァイグアは貨幣のしるしでもあるのだから、さらなるヴァイグアを所有するために他に与えてしまった方が得である。それらは商品やサービスになり、再び貨幣へと形を変えるからである。全く、トリブリアンドやチムシアンの首長は、流動資本を立て直すのに適切な時に貨幣を手放す資本家のやり方を実施していると言えるだろう。利益追求と無私無欲は、こうした富の循環形態と、その後に続く富のしるしのアルカイックな循環形態を等しく説明している。
富すべての破壊でさえ、そこに見出されると思われるような、利益への完全な無関心に応じて行われるものではない。こうした度量の大きな行為ですらも利己主義を免れていないのである。単に贅沢で、殆どいつも誇張されており、大抵な場合に全くの破壊が行われるような消費の形態は、これらの制度に不経済極まりない出費ち稚拙な浪費をいう表情を与えている。
しかしこのような贈与や凄まじい消費、さらに度を外れた富の浪費や破壊は、特にポトラッチの諸社会において、利益追求と全く無関係な契機によって行われるのではない。首長とその部下のあいだ、部下とさらにその追従者のあいだで、こうした贈与によって階層性が作られるのである。与えることが示すのは、それを行う者が優越しており、より上位でより高い権威者であるとことである。つまり、受け取って何のお返しもしないこと、もしくは受け取ったよりも多くのお返しをしないことが示すのは、従属することであり、被保護者や召使いになることであり、地位が低くなること、より下の方に落ちることなのである。
最高位になること、最も立派になること、一番幸運に恵まれること、誰よりも強くなること、最も豊かになること。問われているのはそうなるための方法である。貰ってきたものを後に部下や親族に再分配することで、首長は彼のマナを堅固なものにする。首飾りには腕輪を、訪問には歓待を返すなどして、彼は首長間での地位を保つ。このような場合、富はあらゆる観点からみて有用物であり、それと同時に権威の手段である。果たしてわれわれの場合、これと異なっているだろうか。われわれにおいても、富とは何よりもまず他者を支配する手段なのではないだろうか。
贈与や無私無欲の観念と対置してきたその他の観念、そなわち、利益の観念、有用の個人的追求の観念である。
蓄財が行われるのは、消費するため、「親切を施す」ため、もしくは「隷属者」を獲得するためである。他方、交換の対象は特に贅沢品、装飾品、衣服、あるいは直ちに消費されるもの、饗宴に限られる。貰った以上のものが返されるが、それは最初の贈与者もしくは交換者を屈服させるためであり、単に「引き伸ばされた遂行」による損失を埋め合わせるためではない。利益もあるが、それはわれわれを動かすものと利益と似ているが同じではない。
人を労働に向かわせる一番の方法は、自分たちのためと同時に他人のために誠実に果たした労働によって生涯、公正に賃金が支払われると確信させることだと人々は気づいている。自分たちは生産した以上のもの、もしくは労働時間以上のものを交換している。そして、時間であったり命であったり自分自身の何らかを与えていると生産者=交換者は改めて感じている。常に意識していたのであるが、今度は明確に意識しているのである。したがって、生産者=交換者はこの贈与が適度に報われることを望むのである。この報いを行わない場合、怠惰と生産性の低下を招くことになる。
3 一般社会学上および道徳社会学上の結論
諸社会は、社会やその従属集団や成員が、それだけ互いに関係を安定させ、与え、受け取り、お返しすることができたかに応じて発展した。交換するためには、まず槍から手を離さなければならない。そうして初めて、クランとクランのあいだだけでなく、部族と部族、民族と民族、そしてとりわけ個人と個人のあいだにおいてでも、財と人の交換に成功したのである。その後になってようやく、人々は互いに利益を生み出し、共に満足し、武器に頼らなくてもそれらを守ることができるようになった。こうして、クランや部族や民族は虐殺し合うことなく対抗し、互いに犠牲になることなく与え合うことができたのである。これこそが彼らの知恵と連帯の永遠の秘密の一つである。
これの他に別の道徳、経済、社会的実践は存在しない。
諸民族、諸階級、諸家族、諸個人は豊かになることはできるだろう。しかし幸福になれるのは、円卓の騎士団のように共通の富の周りに座ることができた場合のみに可能である。善や幸福を遠くまで探しに行っても無駄である。それが存在するのは、平和状態、公共のためと個人のためとに交互にリズムよく行われる労働、蓄積され再分配される富、教育によって身につく互いの尊敬と寛大さの中なのである。
道徳的な結論、より正確に言えば、-古い用語を再び用いるなら-「礼儀正しさ」、また今言われているような「公民精神」という結論をいかにして導きうるのかさえも明らかになる。
これらの意識的な舵取りは最高度の技法、つまり、ソクラテス的な意味での「政治」なのである。