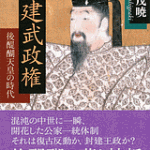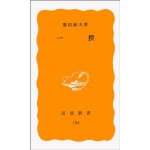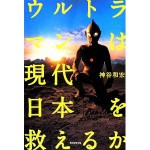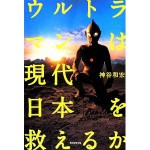 ウルトラマンは現代日本を救えるか
ウルトラマンは現代日本を救えるか
神谷 和宏 著 『ウルトラマンは現代日本を救えるか』 を読む。
第1章 1960年代 「大きな物語」とウルトラマン
超越者としてのウルトラマン -1960年代「イデオロギーの時代」の中で-
初代ウルトラマンと後のウルトラマンたちとの違いは、超越性にあります。人間としての弱さや未熟さ、さらには苦悩すら、ほぼ露呈することなく、超越的なキャラクターとして描かれたウルトラマン=(人間時の)ハヤタ。
かつて、神の存在が信じられていた時代には、大衆が神という一点へ信仰の気持ちを向けることで(社会のベクトルが一方向に向き)階層や秩序が成り立っていたが、神への信仰が迷信と化した時代においては、イデオロギーが(人々を統括するような)超越性を持つ。
神の不在が暴かれた近代社会では、人間ではなく、何らかのイデオロギーが超越者のごとく大衆の頭上に掲げられ、そのイデオロギーの実現に向けて人々が結集するという構図が見られました。
このように、王権やイデオロギーが健在であった時代、人々は自分たちを統べる超越者の存在を認めます。『ウルトラマン』が登場した1960年代は、「政治の季節」、イデオロギーの時代でした。
大衆からその権威を疑われることのないウルトラマンと科学特捜隊。彼らが超越者として存在できたのは、イデオロギーに満ちた60年代という時代性と無関係ではない。
第2章 1970年代 ポストモダンのウルトラマン
臨界点としての1970 太陽の塔とウルトラマン
「万国博覧会の太陽の塔とウルトラマンが似ている。」という指摘が古くからある。(仏文学者 巌谷国士)1970年に開催された万国博覧会のテーマは「人類の進歩と調和」であり、岡本太郎氏はその表象となるオブジェの制作を求められましたが、彼があえて調和に反発して制作したのが「太陽の塔」である。人類が一定の方向に収斂されるかのように調和するという社会の有り様は、岡本の目指すところとは正反対であり、そこであえてあおの左右非対称、調和というコンセプトとはまるで真逆の顔を持った太陽の塔を作った。(あの顔つきは、べらぼうである。)
ウルトラマンをデザインした彫刻家の成田亨氏はコスモス=秩序の象徴として、ウルトラマンのマスクを設定しましたが、作中のウルトラマンはコスモスであると同時にカオス=混沌をも決して排除せず、むしろ分かちがたいコスモスとカオスの間に立つ存在でした。
この万国博覧会は、戦後日本のシステムが「完成」したことへの国民上げての祝祭であり、「戦後日本社会のある種の飽和点を指し示す事件である。」
その理由として、近代における万国博覧会の役目を、魅力的な商品や、革新的な技術、あるいは珍しい異文化という、「イマ-ココ」の「外部」にあるものを見せて、それらを獲得するためのモチベーションを国民に与えることであるはずなのに、1970年の日本社会ではそれらが既に日常のものとなっており、すなわち「イマ-ココ」の「外部」などもはや存在しないことを万博は示したのだ。万博が「国土システムの飽和点、臨界点-最高潮であると同時に死へと歩み始める瞬間」である。(社会学者 北田暁大)
近代とは、神や王の神性を否定し、その代わりに理想の実現という「大きな物語」を設定することで、ツリー的な秩序を維持する時代でした。
戦後の日本ではアメリカが、豊かな国という、わかりやすい「外部」として存在しました。そして、その豊かさを手に入れようと、国民が意識的、あるいは無意識的に「外部」のモノやテクノロジーを取り入れ、自分たちも豊かになろうという「大きな物語」を生きていきました。しかし、そのような豊かさ、すなわち「外部」はもはや、自分たちの内側にあるとわかったとき、国民が同一の外部に向かうベクトルは消失し、代わりに、個々が経済的豊かさを求めることで、やはり「大きな物語」は解体されていくほかなかったのです。
この「大きな物語」崩壊後の『ウルトラマン』シリーズの世界観は、以前の作品の世界観と大きく異なり、上位者の機能不全を招き、リーダーとフォロワー(権力者と服従者、国家と国民)という従前の秩序は解体していきました。
超越者から、未熟な超人へ
人間の上位に位置する超越者として描かれていたウルトラマン(=ハヤタ)と異なり、『帰ってきたウルトラマン』以降の主人公たちは、成長途上の「未熟な超人」として描かれました。
ウルトラマンや防衛隊の面々は、怪獣と戦う以前に、理解のない上司や、大衆と向き合わなければなりません。かつて超越者として存在したウルトラマンや、何だか大らかでさえあった、科学特捜隊の面影はすっかり失われてしまいました。
「光=正義/経済的繁栄=正義」の崩壊
長らく、光とは正義の象徴でした。ウルトラマンの出身地は「光の国」と謳われています。また、光は物質的繁栄の象徴でもありました。都市はその繁栄に比例して光を増します。光はまたエネルギーの消費の象徴でもあり、輝きが途絶えない=眠らない街の登場は、24時間エネルギーが消費されていることを示します。夜でも光り続ける大都市。しかし、そんな経済的繁栄がずっと右肩上がりでいくのでしょうか。エネルギーは無尽蔵なのでしょうか。そのようなことはなく、日本はオイルショックというエネルギー問題に直面し、経済成長は終焉します。
ポストモダンのウルトラマン
「大きな物語」に向かって国民が収束するのが近代であり、「大きな物語」が崩壊した後の世界が「ポストモダン」である。(哲学者 ジャン・フランソワ・リオタール)70年代の4本のシリーズ『帰ってきたウルトラマン』『ウルトラマンA』『ウルトラマンタロウ』『ウルトラマンレオ』は、ポストモダンのウルトラマンであったといえる。「未熟な超人」が「大きな物語」喪失後の日本社会の問題と対峙しながら成長し、超人として人間に何かを伝え、去っていく物語であったと言えます。
オイルショックと大きな物語の終焉
オイルショックは、長期にわたった高度経済成長に終止符を打ちます。オイルショックによる物価高騰は製作費を圧迫しセットを作る費用を抑えざるを得ず、『ウルトラマンレオ』の初期に等身大の宇宙人の描写が増えることになります。
怪獣は巨大なものとして設定されたことで、人々が見上げるべき存在であり、人々に共通して立ちはだかる壁、災厄などの表象として機能しました。
しかし、オイルショックの煽りを受けて、巨大な怪獣の出現シーンが抑えられることで、人々に共通の敵が存在する「大きな物語」の時代が終焉しつつあることを計らずも表象するものになりました。
日本に怪獣が頻出する理由が、「エネルギーに満ちていたから」であり、経済発展していく日本の光と闇を映し出すために怪獣の出てくる物語が構築されてきたのだと考えるのならば、オイルショックというエネルギー危機が、戦後一貫して成長してきた路線に歯止めをかけたとき、そこではもう怪獣が日本に現れる物語は構築される理由を失ったかもしれません。
第3章 1980年代 軽佻浮薄の時代 -ウルトラマンの敗北
ウルトラマン不在の80~90年代 -軽佻浮薄の時代
15年超にも及ぶ「ウルトラマン不在」の期間。最大の理由は制作サイドの問題かもしれませんが、世間が「ウルトラマン的なもの」を欲しなかったからこともあった。
1980年代は、バブル経済への道程でもあり、政治について熱く語るおうな前時代的なスタイルは、「真面目ぶっている」「何だかお堅そう」なイメージとなり、軽佻浮薄を求める世間の風潮とはかけ離れていくようになりました。その時代ごとの政治性が底流する『ウルトラマン』が成立する土壌は失われていまった。
第4章 1990年代 復活するウルトラマンと大いなる闇
環境問題の使者としてのウルトラセブン
単発とはいえ『ウルトラセブン』の続編が作られたことは大きな衝撃でした。
『ウルトラセブン 太陽エネルギー作戦』(1994年)は太陽光発電に代表するクリーンエネルギーの普及を狙う通産省とのタイアップで制作されたものです。ウルトラセブンは太陽をエネルギーとする、太陽の象徴のように描かれます。バブルという酔狂のトンネルを脱し、「80年代的なもの」すなわち「軽佻浮薄」を一掃し、人々が政治性を再び内包するようになった時代だからこそ、『ウルトラ』シリーズは復活しました。