吉岡 忍 著 『日本人ごっこ』 を読む。
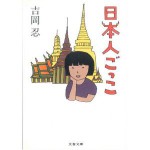
台湾、朝鮮、中国を領有した日本はパールハーバー奇襲と同じ日、香港から東南アジア一帯にかけての侵攻を開始した。当時のタイ軍事政権と同盟を結んだ日本は、ラングーン側とタイ側の双方から兵力を進め、ビルマを支配した。
しかし、戦況はたちまち悪化した。アジア全体と太平洋に広がった占領地域のあちこちで抗日運動が広がり、他方ではアメリカ軍が反攻に転じた。日本本土は空襲で焼かれ、日本軍は玉砕し、潰走した。そして敗戦。日本人の姿は中国大陸からも、他のアジア地域からも消えていった。
その後、日本人がアジア各地に舞い戻ってくるのは、観光客としてではなかった。観光客より前に、アジア各地に姿を現したのは家電メーカーの社員たちだったはずである。
戦後日本の家電メーカーのなかで、外国にはじめて駐在員を派遣したのは松下電器だった。1957(昭和32)年のことだった。それ以前にも他のメーカーが、社員を短期的に出張させることはあったが、駐在員事務所を構えるような本格的な派遣は、同社がはじめてである。
そして、このとき松下電器が駐在員事務所を置いたのは、バンコクだった。タイは戦争中、他の国々のように日本軍に侵略されたわけではなかったので、反日や抗日の気運も少なかったし、戦乱による荒廃もほとんどなかった。日本のメーカーとしては行きやすかったし、市場としても有望と思われたのである。こうしてタイは、戦後の日本企業が世界に向けて製品輸出に乗り出す跳躍の場となった。
当時の日本では、電化の実際の中心はアイロンや扇風機や自転車用ランプ、それに真空管式からトランジスターに変わりつつあったラジオだった。敗戦による荒廃からの復興の時代、そして高度成長期に向かう助走の時代に、これらの製品は文字通り、飛ぶように売れた。大量生産によるコストの低減と価格の低下が、その売れ行きにさらに拍車をかけた。
そのころ、タイで売られていた扇風機やラジオの多くはアメリカやヨーロッパの製品だった。そこに、当時はまだ労賃も安く、大量生産によってますますコストも下がった日本の製品が入りはじめたのである。日本製品の価格は、欧米の製品にくらべて格段に安かった。
しかし、性能や品質やデザインも見劣りするものだった。
松下電器の駐在員の丸田は言う。
「だから私の仕事は、報告するための駐在員でしたよ。バンコクの店先でフィリップス(オランダ)とかテレフンケン(西ドイツ)とかRCA(アメリカ)などの欧米のメーカーの製品を見て、それをスケッチするんです。サンプルを買うお金もなかったですから。私の報告を見て、日本にいる技術者がイミテーションするんです。日本企業の海外進出なんて、最初はそんなふうにはじまったんですよ。」
バンコクからサケオ市などのカンボジア国境沿いの町を通過し、カンボジア国内を通ってサイゴンに入っていくトラックのルートを開拓した日立家電販売の藤田は、「家電製品で大事なのは、モノを売るだけはなく、そのあとの修理などのサービスなんです。戦争中の南ベトナムには延べにして5,60人、常時5,6人の技術者が行ってましたよ。彼らはあっちこっちの基地をまわって、仕事をしていたんです。」
「アメリカ兵たちは運よく戦死せずに、2年間の戦場生活を終えると、故郷に帰ったり、ヨーロッパにあるアメリカ軍基地に転任していった。彼らは南ベトナムで買ったテープレコーダーやオーディオ機器を持っていった。それが、日本のブランドを世界に広める大きなきっかけとなった。」
60年代に入って工業化政策を積極的に進めるようになったタイでは、製品輸入に対する関税を高めたり、輸入禁止品目をふやすなど、自国産業の保護育成をはかるとともに、外国企業に対して工場を誘致するようになった。
藤田は、「販売ルートを調べるために、タイ国内、くまなく歩きまいした。」そして、その過程で発見した大きなルートのひとつが、「スマッグル(密輸)だった。」メサイのように隣国と自由に往来できる国境の町は、タイのなかにいくつでもある。ビルマ、ラオス、カンボジア、それに南のほうにはマレーシアがある。それぞれの国境の町の業者と話をつければ、製品は外国にも流れていく。
これは、外国での現地生産に、当時、まったく不慣れだった日本の家電メーカーにとっては、大きな利点だった。
学生や若者たちにのあいだで、日本のファッションの人気が高いのはなぜだろう。
「私はそれは、文化の量の問題だと思っている。日本の文化情報はファッションだけでなく、車や電化製品や化粧品としても入ってくる。日系のデパートもある。タイでは、アメリカやヨーロッパの文化情報を圧倒している。そこにテレビや雑誌の広告が加わるんだ。日本はいま、ものすごい力で若者たちを引っぱっている。」
無数の「日本」に囲まれて、<ワタシはタイ人ですか?>とつぶやく歌の先を探っていけば、その社会がオリジナリティをどう築いていくのか、という問題にたどりつく。いや、そのことのむずかしさにたどりつくと言うべきかもしれない。
私が私である根拠を築こうとするものを無力感に追い込み、自信を失わせ、むなしさに囲い込む力としての「日本」が、ここにはある。
先進国や経済大国というものの力。それは経済や産業の分野にとどまらない巨大な力である。私が私である根拠を揺さぶり、ときには無力感さえ植えつけるその力は、人々を混乱に落としいれ、その社会全体に外側から変貌を迫っていく。
変わりつつあるタイの現在を、これは進歩への過程であり、繁栄への途上なのだとなかなか楽観できないのは、この問題に関わっている。これらは彼らの問題ではなく、先進国の中で働き、経済大国のなかで生きている私たちの問題である。

この本は、とても面白そうですね。
今は韓国なのでしょうかね?
ぐるめ、コスメ、音楽、電化製品も韓国のほうが強くなっていますね。
日本も小さな国だけど、韓国はより小さい国なのに昔の日本のように
勢いがありますね。