中沢新一 著 『古代から来た未来人 折口信夫』 を読む
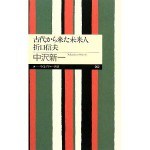
第一章 「古代人」の心を知る
姿を変化する「タマ」
折口信夫の考え方では、「神」という考えは、超越的な存在について日本人がつくってきた概念のうちでも比較的新しい層に属する考え方で、もっと古い原初的な表現は「タマ」と呼ばれる霊力にかかわっていた。
「タマ」は「神」とちがって、増えたり減ったりする。「神」のような特定の性格づけも機能も持たない。明確な名前も持たないし、変幻自在でいっときなにかのかたちであらわれたかと思うと、すぐに別のかたちをしたものに変身していってしまう。「神々」はしばしば体系のなかに組織されて、国家のために役立つ存在になる。ところが「タマ」のほうは、なかなか体系につかまってしまうことがない。「タマ」はしばしば威力のある動物と結びつく。しかし「神」はそれよりもずっと人間化の度合いが強い。太陽の霊力をあらわしていた「タマ」的な存在が、アマテラスという女神になっていくと、自然との濃密な結びつきは希薄になって、いつのまにか政治権力と結びついてしまう。ところが、どんどんすがたを変えていったり、一定の居場所を持たなかったり、半分自然のなかに身をひたしている「タマ」は、人間化の度合いがずっと低いのである。
日本人が超越的なものや力について考えてきた歴史を考えてみると、「神」という考えは表面の層に属していて、その層の奥には「タマ」という考えがひそんでいる。漢字を使ってその「タマ」を「霊力」と表すとすれば、「神」よりも原初的な、おおもとの存在として「精霊」が浮かび上がってくる。この「精霊」は、「古代人」の思考法である「類化性能(アナロジー)」との相性がとてもいい。体系のなかでの名前や場所を持っている「神」は、宗教的なものごとに「別化性能」が働くときに生まれてくる考え方である。ところが、流動する液体のような「精霊」には、合理的な思考を生む「別化性能」はうまく働かない。別のものとくっついて新しい存在をつくりだしたり、ものごとの境界に潜り込んでいける「精霊」をとらえるには、芸術をもうみだすことのできた「類化性能」しか、有効には機能しないからである。
精霊ふゆる「ふゆ」
折口信夫は日本列島における「古代人」の、宗教性ゆたかな暮らしを、つぎのようなサイクルとして描き出した。「古代人」は月の満ち欠けと太陽の位置に、とても敏感に反応していた。月の満ち欠けは、一月ごとの周期的変化を作り出す。これにたいして太陽は昼と夜の長さを変化させながら、一年を単位とする大きな周期を描いていく。春分と秋分には昼と夜が同じ長さになる。冬至には昼の長さが一年でもっとも短くなり、夏至にはもっとも長くなる。多くの祭りが、昼と夜の長さがもっともアンバランスになる冬至と夏至に集中しておこなわれる。
この冬至と夏至をはさんで、「古代人」は精霊(スピリット)をこの世にお迎えする祭りをおこなう。夏至をはさんだ夏のお祭り期間には、死霊のかたちをとった精霊の群れが、生きている者たちの世界を訪問してくる。死霊には、まともな死に方をして、しかも子孫たちから敬われつづけている先祖の霊もいれば、横死をとげたり幼い子供のうちに亡くなってしまった者たちの浮かばれない霊もいる。そういう多彩な死霊たちが大挙して戻ってくるのを、「古代人」は心をこめてお迎えしようとしたのである。
その夏の時期の精霊来訪の祭りは、のちのち仏教化されて、お盆の行事となったけれど、そこには「古代人」の思考の原型がはっきり残っている。お盆の行事としておこなわれる「盆踊り」を見てみよう。盆踊りの古いかたちを見てみると、村の人々が村の外からなにか目に見えない霊を迎え入れ、渦を巻きこむようにして踊り始める。生きている者と精霊がいっしょになって、円陣をつくってグルグルと村の広場で夜を徹して踊るのである。精霊とともにすごした幾夜かがすぎると、人々は円を解いて、そのまま村はずれまで列をなして行進していく。そして村はずれの川や埋葬地の近くで、精霊を切り離す儀式をおこなうのである。この期間、立派な祖霊もすこし危険なところのある亡霊も、大切な訪問客として、ていねいにもてなされる。夏の精霊の祭りでは、客人である霊はまったく人間の訪問客のもてなしと同じ考えで、迎え入れられるのだ。
冬至をはさんだ一、二か月は、その昔は霜月と呼ばれて、やはり精霊を迎える祭りがおこなわれた。しかし冬の期間におこなわれるこの祭りでは、夏の精霊迎えの祭りとはちがった考えが支配的だった、というのが折口信夫の考えである。この期間、精霊の増殖と霊力の蓄えがおこなわれるのである。折口信夫の考えでは、「冬(ふゆ)」ということばは、古代の日本語に直接つながっている。「ふゆ」は「ふえる」「ふやす」をあらわす古代語の生き残りなのである。
冬の期間に「古代人」は、狭い室のような場所にお籠りして、霊をふやすための儀礼をおこなっていた、だからその季節の名称は「ふゆ」なのである。人々がお籠りをしている場所に、さまざまなかたちをした精霊がつぎつぎに出現してくる。このとき、精霊は「鬼」のすがたをとることが多かった。
第二章 「まれびと」の発見
「あの世=生命の根源」への憧れ
「まれびと」の二つ目の意味は、「あの世」からの来訪者ということに関わっている。人間の知覚も思想も想像も及ばない、徹底的に異質な領域が「ある」ことを、「古代人」は知っていた。つまり、世界は生きている人間のつくっている「この世」だけでできているのではなく、すでに死者となった者やこれから生まれてくる生命の住処である「あの世」または「他界」もまた、世界を構成する重要な半分であることを、「古代人」たちは信じて疑わなかったのである。
この他界と現実の世界をつなぐ通路が発見されなければならない。目にも見えず、思考がとらえることもできない「あの世」から、なにか不思議な通路を通って「この世」に出現してくるものが、うまく表現されたとき、人は不幸な感覚から解放される。「この世」に生きている時間などはほんのわずかにすぎないけれど、それでも「この世」を包み込んでいる「あの世」があり、あらゆる生命が死ぬとそこに戻っていき、またいつかは新しい生命となって戻ってくることもあると知ることができれば、わたしたちはいつも満ち足りて落ち着いた人生を送ることができる。「あの世」と「この世」をつなぐ通路こそ、折口信夫の発見(再発見)した「まれびと」なのであった。
第三章 芸能史という宝物庫
「翁」という能のもっとも重要な演目は謎に満ちている。「翁」という演目は能がまだ「猿楽」と呼ばれていた頃から、もっとも秘密性の高いものだと考えられてきた。しかしなぜ「翁」のように単純きわまりない構成の芸が、それほどまでに神秘とされていたのか、折口信夫はその芸態が「あの世」からの精霊出現のさまを様式化してしめしたもでのあるからだ、と考えた。
「この世」の現実とはまったく違う構造をした「あの世」の時空との間に、つかの間の通路を開いて、そこからなにものかが出現し、また去っていき、通路は再び閉ざされる。その瞬間の出来事を表現したものが「翁」である。「古代人」は自分たちが健やかに生きていけるためには、ときどきこのような通路が開かれ、そこを伝って霊力が「この世」に流れ込んでこなければならないと、考えていた。「翁」という演目は、そういう古代的な儀礼のかたちをそっくり保存しているのである。
芸人はそのような精霊を演じているわけだから、とうぜん一瞬開かれた通路から流れ込んでくる「あの世」からの息吹に、触れていることになる。「あの世」には恐るべき力がみなぎっている。現実の世界ではかろうじて抑えられていた力が、死によって解放されると、その力は「あの世」に戻っていく。芸能者は、このように死と生命とに直に触れながら、ふたつの領域を行ったり来たりできる存在なのである。
芸能者は死者たちの息吹に直に触れている。それと同時に、芸能者は若々しく荒々しいみなぎりあふれるばかりの生命力にも素手で触れている。彼らの芸は、生と死が一体であることを表現しようとしている。別の言い方をすれば、芸能者自身が死霊であり荒々しい生命でもあるという矛盾をしょいこんでいる。だから、彼らはふつうの人たちとは違う、聖なる徴を負っている人々として、共同体の「外」からやってくる、「まれびと」としての性質を持つことになったのだ。
そのような「芸能者の原像」を「鬼」があざやかに表現している。「鬼」は共同体の「外」からやってきて、死の息吹を生者の世界に吹きかけ、そこに病や不幸をもたらすこともある。しかし、荒々しい霊力を全身から放ちながら出現してくる「鬼」の存在を間近に感じるとき、共同体の「中」で生きている人々は、自分たちの世界に若々しい力が吹き込まれ、病気や消耗から立ち直って、再び健康な霊力にみたされ、生命のよみがえりを得ることができたようにも感ずるのである。ふだんは「鬼」を恐れて近づけないでおこうとしている人々が、お祭りの興奮の中ではむしろ競って「鬼」に近づき、その荒々しい息吹に触れようとしている。このとき折口信夫は「古代人」のおこなった「野生の思考」の末裔である芸能者の運命を思った。
