柳田 邦男 『「人生の答」の出し方』 を読む
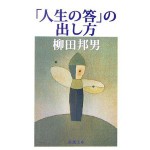
人が生きる時間
人生の「生きられた時間」
私の中に二つの異質な時間が流れていたのだ。一つは、私だけが個人的に直面している現実と結びついた「一人称的な時間」。そして、もう一つは、主観的な感覚や意識に関係なく、誰の上にも共通に流れている客観性を持った「三人称的な時間」である。
人間が生きるうえで決定的に重要なのは、「一人称的な時間」の中で、「生きられた時間」を持てたかどうかということだった。「生きられた時間」とは、哲学者ウジューヌ・ミンコフスキーが提唱した概念だ。
だが、情けないことに、次男が死んで、自分が離人症的な精神状態を経験してはじめて、「生きられた時間」が持てないというのは、ずっと深い実存的な苦しみであったのだと、ようやく実感のレベルで理解できるようになったのだった。
こうして「一人称的な時間」や「生きられた時間」というキーワードを手にしてからは、がんや難病などの厳しい病気と闘いながら懸命に生きている人々に生き方を見る眼をより深めることができるようになったと思う。
最近、がん患者たちがよりよく生き抜くための「生きがい療法」が、少しずつ広まっている。
生きがい療法の基本方針五項目の中で、とくに注目したいのは、次の三つの心得だ。
1)ただ生きようと思うのではなく、自分が自分の主治医になったつもりで、病気をしっかり見つめて、前向きな姿勢で治療を受け、がんと闘っていくこと。
2)今日一日の生きる具体的な目標を自覚して、全力投球すること。
3)人にためになることをすること。
このような闘病の姿勢と生き方を次のように表現することができるだろう。すなわち、進行がんになったからといって、絶望したりうつ的になったりして人生を投げ出すのではなく、あるいはただいたずらに生物的な延命(=三人称的な時間の延命)を求めて医師任せの治療を受けるのではなく、自分が直面している厳しい病気の現実に結びついた大事な日々、つまり「一人称的な時間」を可能な限り密度の濃い「生きられた時間」にするべく、主体性をもって治療に臨み、生きがいを実感できる日々を設計していくならば、納得することのできる「これが私の人生だ(This is my life!)」という物語を書けるに違いない。しかも、そういう生き方を貫くならば、唯々諾々と治療を受けているよりも、結果として、はるかに大きな延命効果を獲得することができるにちがいない-と。
このことは、人生の長さとは何か、ひいては本当の長寿とは何か、という本質的な問題について、一つの答を出していると言えるのではないかと、私はとらえている。
そして、私は、次のようなモデルを考えている。
「人生の長さ(意味のある人生の長さ)」=「生きられた時間の長さ」x「その密度」
ここで一つ、補足しておくべき大事な問題がある。それは、生きがい療法の方針の中にある「人のためになることをする」が、なぜ厳しい病気を背負った自分の生を支えることになるのか、その意味についてだ。
この問題について、最も鋭く明快な解答を出したのは、第二次大戦中のナチス・ドイツの強制収容所で生き残った精神医学者ヴィクトール・E・フランクルだ。飢えと強制労働とガス室による大量殺戮という絶望的な限界状況下で、人格を崩壊させずに生き抜くことができた人々を支えた考え方はどんなものだったのか。フランクルは、『夜と霧』の中で、劇的に気づいたことについて、こう書いている。
<人生から何をわれわれはまだ期待できるのかが問題なのではなくて、むしろ人生が何をわれわれから期待しているかが問題なのである。>
<われわれが人生の意味を問うのではなく、われわれ自身が問われた者として体験されるのである。>
限界状況の中で絶望しないためには、生きる意味についての考え方を180度転換させること、すなわち「人生の問いのコペルニクス的転回」が求められるというのだ。

別途解説もとめます。