寺田 寅彦 著 『天災と国防』を読む。
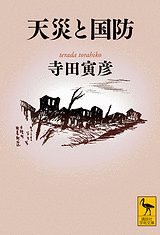
解説・畑村洋太郎
どんな事柄や現象を見る時も同じだが、対象の正しいモデルを自分の中につくるときに欠かせない必須の視点というものがある。
大まかにいうとそれは、「構成要素」「マイクロメカニズム」「マクロメカニズム」「全体像」「定量化」「時間軸」という六つの視点である。
まず、第一の視点は構成要素である。これは観察対象がどんな構成要素から成り立っているかを知ろうとする視点である。
第二のマイクロメカニズムは、観察対象が動作をするとき、その現象を起こしている要因を考え、その関連がどのようになっているかをメカニズムとしてとらえる視点である。
そして第三のマクロメカニズムは、全体の構成要素がどのような関連で、どのような支配法則によって動いているかを捉える視点である。
マイクロメカニズムやマクロメカニズムは、観察対象や現象だけに注目する視点である。それが外から見たときに全体としてどのように見えるとか、どのように動くのかを知ることが必要なのである。これが第四の全体像を見る視点である。
第五の定量化は、対象や現象を量的に捉える視点である。これは自然現象や技術などを捉えるときには必須の視点である。
第六の時間軸も、先ほどの定量化と同じく忘れがちな視点である。すべての事柄や現象は未来永劫に不変ということはなく、必ず時間とともに変改している。
「三現」と「三ナイ」
三現というのは、ある事柄や現象の正しいモデルを自分の中につくるために不可欠な観察の基本姿勢である。
具体的には、「現地」「現物」「現人」の三つの姿勢を指す。
要するに「現地」まで足を運び、そこで「現物」を直接見たり触れたりしたり、「現人」(現場にいる人)の話を聴くということである。
インターネットをはじめとする各種メディアが充実しているので、それらの情報を見るだけでかなりのことがわかる。
しかし、ここには大きな落とし穴がある。「百聞は一見に如かず」で単に頭に仕入れる事実と実際に現地に行ったりして生で触れる事実が大きくちがうことも往々にしてあるのだ。
メディアや専門家などw利用しながら対象とする事柄や現象を理解する方法はいかにも楽そうに見える。しかしこれは、大きな錯覚である。
私はこのような姿勢を「三ナイ」と呼んでいる。
「見ない」「考えない」「歩かない」という意味で、これらは三現の対極にある観察姿勢である。三ナイは手っ取り早い方法のように思われがちだが、もともと大きな問題があるのだ。そもそも三ナイには本当の知識を体得するために必要な、目的意識を持って行動したり、実際の体験の中で自分自身でなにかを感じたり自分の頭で主体的に考える姿勢が欠けているのである。
「三日、三年、三十年、三百年」(人間の法則)
人間の忘れっぽさを考えるときには「三」という数字がカギになる。
「三日坊主」という言葉があるように、人間は同じことを「三日」も繰りかえすと大抵は飽きてしまう。自分が被災者になって手痛い被害を直接受けたときには、さすがにもう少し記憶が長続きするが、それでもふつうは「三年」もすればだんだんと忘れていくようである。
組織の場合になると、個人とちがって記憶がもう少し長続きする。ただし、組織には、長く活動を続けている間に必ず人間の入れ替わりがあるという特徴がある。そこで記憶の減衰が必ず起こる宿命にあるのだ。
大きな事故やトラブルの記憶でも、たいていは「三十年」もすると減衰していくのが一般的である。
一方、社会の場合は、個人や組織のときとちがって被災の記憶は記録としてかなり長く残る。それでも一定の期間を過ぎると、個人や組織のときと同じように過去に経験した危険をだんだん数のうちに入れて活動をしなくなる傾向があることには変わりない。社会の中で大きな事故やトラブルの記憶が減衰するのは、だいたい「六十年」程度である。そして、その状態が続いて「三百年」もすると、社会の中でそのことは「なかったこと」として扱われるようになる。さらにいうと「千二百年」も経つと、そのことは文書に書かれている場合を除いて、社会の中で完全に「なかったこと」になってしまい、人々の意識から完全に消え去ってしまうのである。
「もう津波は天変でも地異でもなくなる」。これは地震に対しても同じだが、「過去の習慣に忠実で」、「新思想の流行などには委細かまわず、頑固に、保守的に執念深くやって来る」ものとして見る必要がある。
「内部基準」を備える
いざというとき使える知識を身につけることを勧めているのである。
ここでいっているのは、自分の行動を自分で決めるときに欠かせない「内部基準」を備えろということである。これを「漠然たる概念でもよいから、一度確実に腹の底に落ち着けておけば、驚くには驚いても決して極度の狼狽から知らず知らず取り返しのつかぬ自殺的行動に突進するようなことはなくてすむ」と書いている。
一般的な安全対策は「マニュアル主義」で行われているが、寺田が指定しているのこのやり方の危うさである。「このルートを通れば安全」として通るべきルートを示し、それ以外は一切通ることを許さないのがマニュアル主義の考え方である。このやり方でも安全は確保できるが、これには環境の変化などなにかの拍子にそのルートが使えなくなると、途端に無力になるというもろさがある。それはマニュアルを使う人が与えられたルート、つまり「外部基準」だけに頼っているからで、これでは変化が生じたときの新たな状況にまったく対応できず、なにもできない思考停止状態に陥ってしまう危険がある。
この状態で再び外からなんらかの支持が与えられると、それがおかしなことでもその人はなんの疑問も持たずにそのとおりの行動を始めてしまうこともある。
想定外の問題が生じたときに自分の行動を決める内部基準がないから、外から入ってくるおかしな情報に簡単に振り回されてしまうのである。
福島第一原発について
技術論でいうと、原子力はかなり安全なものになってはいるが、基本的な視点が欠けているように見える。それは安全の実現手段は、基本的に「制御安全」に依存し、「本質安全」の考え方を取り入れられていない点である。失敗やトラブルが起こったとき、自動的に安全の側に働くような仕組みをつくらず。制御技術によってコントロールしよとしていたのである。制御安全のみに頼る方法は、想定外の問題が起こったときには非常にもろいが、このような基本的な問題があるのに、建前としての安全を真実安全だとして議論していたことが問題なのである。
安全対策というのは、危ないことを前提に動いているから効果のあるものになる。安全であることが前提になると、管理が形式的なものになって意味をなさなくなってしますのだ。それでも国から与えられた外部基準、すなわちマニュアルがあればなんとかなると思うかもしれないが、マニュアルは想定している条件の中でのみ力を発揮する。今回のような想定外の問題が生じたときには非常に無力なのである。
想定外の問題が起こったときに正しく対処を行うには、進むべき道を自分で考えるための内部基準が必要になる。
この事故は想定外の問題に対処できるための内部基準を備えることを怠った「組織不良」によるものであるのは間違いないのである。
災難を成長の糧にする
「人間の動きを人間の力でとめたりそらしたりするのは天体の運行を勝手にしようとするよりもいっそう難儀なこと」なのである。
治山や治水、砂防などにかかわっている土木技術社の間では、「既往最大」といって過去に認められている実際に起こった災害を想定して対策を行うのが暗黙の常識になっている。
じつは福島第一原発で想定している津波が「低すぎるのではないか」という指摘はかなり以前からあった。貞観地震の研究者が根拠を示しつつ、東京電力や国に対して危険性を伝えていたのである。この忠告が無視されたのは、人間の法則のなせる業である。無視した人たちに特別な悪意があったとは思えないが、「見たくないものは見ない」「考えたくないものは考えない」かた、忠告を聞いても心が強く動かされることなく、結果として黙殺してしまったということなのだろう。
