高橋 源一郎 著 『ニッポンの小説 百年の孤独』 ちくま文庫 を読む
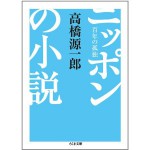
「ニッポンの近代文学、百年の孤独」(プロローグ)
19世紀後半、封建的な世界が崩壊して、新しい政府が誕生した時、この小さな東の国は、とてつもない変化を被ることになりました。そして、生き残るために、西洋社会の文物を輸入されました。かくして、科学技術や社会システムが、そして文化が輸入されました。その中にはもちろん、「文学」も含まれていました。
重訳というのはとても興味がある現象です。一つの言語から、もう一つの言語へ、そこからさらに次の言語へと、移し変えられる度に、元の言語が持っている困難さはすり減っていき、言葉は透明になり、伝えやすいものだけが伝わることになります。あるいは、誰にでも使える言葉へと変わっていきます。
もちろん、ここでもベンヤミンが「翻訳者の使命」と呼んだ、あの有名なフレーズは有効です。
「ある容器の二つの破片をぴたりと組み合わせて繋ぐためには、両者の破片が似た形である必要はないが、しかし細かな細部に至るまで互いに噛み合わなければならぬように、翻訳は、原作の意味に自身を似せてゆくのではなく、むしろ愛をこめて、細部に至るまで原作の言いかたを自身の言語の言いかたのなかに形成してゆき、その結果として両者が、ひとつの容器の二つの破片、ひとつのより大きい言語の二つの破片と見られるようにするのでなくてはならない。」
ベンヤミンの、翻訳に関するこの断言は、おそらく、完成した言語、長い伝統の果てに成立した言語間の受け渡しについていわれたものです。しかし、そうではなく、完成した言語から、新しい言語へ、未だ始まっていない言語への受け渡しにこそ、この断言は、より一層あてはまるような気がするのです。そこでは、単に一つの作品から、もう一つの作品へ「翻訳」が行われるのではなく、「翻訳」を通して、規範となる「文」そのものが、元の言語の反対側に産みだされるのです。
「ニッポン近代文学」という集落で話されてきた言語は、国木田独歩の「文」、それにの先駆たる、二葉亭四迷の「文」から流れ出たものです。それは、ほとんど変化することはありませんでした。
不思議なのは、「ニッポン近代文学」という集落は、実に多くの「外部」の侵食を受けているのに、つまり、外国文学や、文学以外のさまざまなものに影響を受けてきたのに、孤立しているように見えることです。
ところで、「文学」とは何でしょうか。
「文学」とは、遠くにある異なったものを結びつける、あるやり方のことです。なぜなら、「文学」は、言語だけで出来ていて、しかも、言葉とは、要するに、遠くにある異なったものを結びつけるために出来たからです。
言葉は、物と観念を結びつけます。名前と事象を結びつけます。存在しないものと存在するものを結びつけます。関係づけることが不可能に見えるものを、いとも簡単に関係づけます。
我々がコミュニケートするためには、言語が必要なのです。もちろん、言語以外にも、コミュニケートするツールはあります。映像がそうです。貨幣もそうです。いや、貨幣は言語そのものなのです。そして、資本主義社会では、貨幣も言葉も、絶えず価値の変動に晒されなければならない、というわけです。
だから、『資本論』に「文学」の一切が書いてるということもほんとうです。言葉というものが、どうやって産み出され、異なった共同体をどう結び付け、どう流通し、それが集まって巨大な塊になり、その結果、一つ一つの言葉を抑圧するようになるのか、それらはすべて、あの本の中に書いてあるのです。
二葉亭四迷が作った「器」に、若者たちが「文学」を充填しはじめる時が来ました。
いくつもの言語が存在するということは、つまり、翻訳というものが必要であるということは、「器」は絶えず壊れ、それ故、絶えず修復されなければならない、ということを意味している。
言葉が混乱の只中に陥った時、はじめて、我々は「文学」を必要とするようになった。「文学」とは、「器」を作り、そして壊す、その一連の行いそのものではないでしょうか。
