天稟豊でいっしょに夕飯。

いつもの海老と豚肉の焼き餃子 と小龍包、エビワンタン麺を注文する。
飲み物は、あったかい烏龍茶。ポットで飲めて、無料。

レンゲにのせて、皮を破いて出汁を味わう。
あったかいうちに食べる。

あっさり出汁に細麺。
青梗菜とネギが入りのワンタン麺。
飽きずに食べられる。

梅田散歩

梅田第3ビルの地下2F
とまとラーメン信濃路で
いっしょに夕飯。
スープスパゲティといった食感。
トマト味のスープにセロリの風味。
キャベツを縦に割ったものをコンソメスープとホールとまととソーセージを一緒に煮た料理の味を思い出した。

お店の外観写真を載せておく。
竹下 節子 著 『キリスト教の真実』 を読む
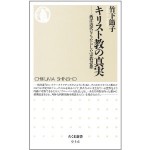
第二章 暗黒の中世の嘘
新しい思想は古い思想を仮想的としてみずからの正統性を主張する
近代の成立において、主としてプロテスタント勢力がローマ・カトリック教会を「敵」と見なし、その地位を貶めることによって自らの正統性を証明しようとした。
知を共有財とみなすキリスト教の教育
シャルルマーニュは、「知性」の必要性は、エリートだけでなく、庶民にも求めらるべきとだとして、「無償の学校」制度を設けた。
学校制度が可能になったのは、各地で「蛮族」の襲撃を逃れた多種多様の書物が、あらゆる教会堂や修道院へすでに避難させられていたからである。600年から750年の間にフランク王国内だけでも200の僧院が建てられた。シャルルマーニュの誕生からその孫の死までの期間(768-855)には、27の司教座聖堂(カテドラル)が建ち、417の修道院が建設された。偶像崇拝禁止であったが、読み書きできない民を教化するために、カテドラルや修道院は新旧聖書の図像で豊かに飾られた。
これら「知の流通」は、キリスト教の普遍主義に支えられていた。キリスト教においては、知は個人財産とみなされず、修道院図書館などに保存され、書写によって複本がつくられ、古典学術が継承されていった。背景には、キリスト教には全ての人間の自由意志を前提とした教育理念が備わっていたことがある。
修道院に付属学校が開設された後に、司教区の学校が作られる。司教区学校は聖職者養成のためだけにできたのではない。学校に集った若者にはラテン語の基礎や教養科目が教えられ、古典学術を継承するために不可欠な素養を身につけさせた。カリキュラムは、文法、修辞、弁証(論理)の三学と算術、幾何、天文、音楽の四科から成り立っていた。一方で神学の教育は聖職者の身分を擁する者のみに与えられていた。
大学の誕生
大学(ユニヴァーシティ)は、カトリック教会がヨーロッパ中に設置した教育研究機関だった。ユニヴァーシティの語源は、普遍=カトリックと同じものだ。教会という言葉が「教会堂」の建物を表すのではなく聖職者と信者の集まりを意味していたように、ユニヴァーシティも、教授と学生の共同体を意味するものであり、講義はカテドラル(司教座のある教会)の内部や私邸の中で行われていた。ローマ教皇はこのユニヴァーシティの監督保護者であり、教授に対する支払いが滞るなどの苦情が教皇にまで持ち込まれて処理されていた。
大学の誘致は経済効果があるため歓迎されていたが、学生を含めた大学関係者は消費者として地域経済に貢献するが、定住の意思を持たない「よそ者」であり、生産者でない。彼らは対等な市民とはみなされず、住居、食物、書物などの売買で騙され、警官からは暴力をふるわれた。そのような敵意から大学を保護するために、ローマ教会はかれらに「聖職者(clericus)」の身分を付与した。「聖職者に対する暴力」は、世俗でも犯罪とされ、聖職者自身は原則として教会の法廷によってのみ裁かれる地位を与えられた。この「大学」のおかげで、聖職者=知識人という構図がかたちつくられるようになった。
当時の大学は、14歳からの中等教育も受け持ち、庶民家庭の子弟が少なくなかった。三学四科の教養科目(リベラル・アーツ)と哲学(リベラル・アーツを統合して神学の予備となる高度な論理的思考だった)を修めた後で、さらに法学(世俗法と教会法)、自然哲学(自然科学)、医学、神学を学ぶことが可能だった。ラテン語で出回るようになったユークリッド幾何学、アリストテレスの哲学や自然学、ガレノスの医学書などが教科書として使われた。
ユニヴァーシティにおける教育機関はスコラ(scolas)であり、そこでの教育がスコラ学という方法論になった。社会の変化に応じて学問の方法が大きく変わっていった。教師たちは単に古典の購読だけでは満足できなくなり、理性を重視し、主論と反論を戦わせて結論を導く弁証法的な主知主義を用いて深い意味を汲もうとした。まず問いがたてられ、互いに反する仮説が提示され双方の議論の妥当性を検討し、自分の結論を提示したうえで、反論に答えるという形式が、次第に確立していった。スコラ学の誕生である。
第三章 「政教分離」と「市民社会」と2つの型
カトリックとプロテスタントの棲み分けは、次のようにおこなわれた。
ローマ・カトリックのホームグラウンドであるイタリアは、カトリックのまま。イベリア藩半島も15世紀末に達成されたレコンキスタによってカトリック陣営が強力だったため、カトリック圏にとどまった。10世紀以来神聖ローマ帝国皇帝を選挙で選んできたオーストリアからドイツ、中欧に及ぶ地域は、ハプスブルグ家がカトリックを維持し、他の領邦国家は、カトリック公とプロテスタント公に分かれた。1648年のウェストファリア条約以来、各国の領主が帰依した宗派が国の宗教となり、他の宗派の信者たちは、改宗か移住をすることで棲み分けを維持した。
絶対王権下にあったイギリスとフランスでは、どちらの王も宗教的権威のトップに立つカトリック教会と拮抗しようとしてきた。ヨーロッパ中をネットワーク化している教区と司教区と修道会を束ねるローマ教皇に対抗するには、主に3つの方法が考えられる。
①国内の司教や司教区や修道会長の任命権を獲得して血縁者に委任する。
②ローマ教会と断絶して国内のインフラをそのまま流用して王が「国教会」の長となる
③教会の財産を没収して市民宗教を作る。
フランスは最初の方法を選んだ。つまり、司教の任命権を得ることでガリア教会の自律性を確保しようとした。
イギリスは2番目の方法を選んだ。ローマ教皇に破門されて国教会を興した。
すなわち、フランスのおける政教分離は、それまでカトリック教会が一手に担っていたネットワークや社会運動から宗教のレッテルを外し、それらを政府がそのまま継承し、カトリック教会が独占していた利権システムを解消または吸収したものになった。
そのおかげで、フランスの政教分離は、「横割り二層型」になった。すなわち、「公共空間」における「宗教のレッテル外し」を各宗教が認め、宗教行為(あるいは宗教否定行為)と宗教的な信条はともに「私的空間」に追いやられたわけである。このことこそが、共和国主義の「普遍性」の本質である。たとえ「私的空間」であったとしても、その空間が異なる信条を持つ人びとからなる共同体に属しているのであれば、個人的な信条にもとづいたふるまいをすることは許されない。共同体のマジョリティが多数の力でみずからの主義をマイノリティに押し付けることは禁止され、もしそのような事態が生じた場合には、国家が「共和国主義」の普遍理念の名のもとに介入できるという伝統がある。
「民主主義」の概念には「多数決」に従う、というものがあるが、フランスを含めた、「カトリック否定型」の近代を作ってきた国の大きな特徴は、「多数決」よりも「普遍理念」が優先される普遍主義にある。
アメリカという国家は、ヨーロッパでマジョリティをしめるカトリック国家や、そのヴァリエーションとして国教会を持つイギリスを比べると明らかに異質である。
イギリス国教会から迫害されたマイノリティであるピューリタンの男たちによって「開拓」された「新天地」であり、既成の利権システムなどは存在しない世界だった。建国の核となったのは、WASPと呼ばれる白人アングロサクソン・プロテスタントという宗教的なレッテルに強固に結びついた同質の共同体だ。
アメリカのアイデンティティの核は、WASPのそれである。アメリカは「神の国」であり、アメリカの社会でリーダーシップをとるには、「アメリカの神」を掲げ、神の名によってアメリカを祝福することである。アメリカでは、政教分離を「縦割り」にして、宗教は公生活の「両輪」に一つとなる。政治家が所属教会を明らかにし、日曜日のミサに出ることは社会性と道徳性の証明にもなっている。
フランスの民主主義
フランスのおいて、民主主義はフランスの死守する「共和国主義」を担保するツールの一つである。アメリカにおいては、民主主義は功利主義経済システムを担保する「建前」である。フランスの共和国主義とは、出身地や人種や宗教の違いにかかわらず、同じ国に住む人間が、「自由・平等・博愛」という同じ共和国原理を共有し、それを、個人のアイデンティティのうちに理性的に「統合」していくことを目標にしている。
子どもたちはそれぞれの家族や共同体の文化や宗教の影響を受けて育っているが、その偶然の「与件」の特殊性の外側に、「普遍価値」があることが教えられ、普遍性という物差しを基準にして考える思考訓練がなされる。自分の頭で、自分の「与件」について考え、判断するならば、それをリセットして、共同体の価値観や伝統や習慣や文化や宗教を離脱して別のものを選択する自由が存在することを気づかせることが可能である。これが共和国の公教育理念である。
アメリカの民主主義
アメリカの教育の場において最も重要視されているのは、労働市場に見合った生産者、即戦力になる人間を養成することである。アメリカの教育において、「実学」とは別の「道徳」や「倫理」はどこで教えられているかというと、子供たちの生まれて育つ共同体であり、宗教行事の場である。アメリカにおいて「普遍的」なものは、経済活動における数の原理であり、競争原理である。「道徳」や「文化」や「価値観」については、特殊であっても「共同体的」であっても一向に構わない。いやむしろ、「道徳観」を持つ証明、「良心の査証」として、何らかの「宗教」への所属は大切な要素である。教育の場には「民主主義」の言葉と「星条旗」があればいい。
アメリカの政教分離は、功利主義経済を担保する宗教と、それを容認する政治という両輪なのだ。
姫路船場別院に参る。
本徳寺(通称 船場御坊)で、浄土真宗大谷派(東本願寺)のお寺。
西本願寺のお寺として、亀山御坊もある。

表門から入る。

真宗の寺は、屋根が大きい。
本堂は、市文化財。

龍の彫刻もある。

2か所に獅子の彫刻のある。

端は、象の彫刻の飾り。

鐘楼は、市文化財。

裏門は、壊れてる。
お金がないので修理できないようだ。
JR姫路駅から ゼンリン 姫路支店 へ歩いて行く。

姫路のキャラクター「しろまる姫」
の案内がある。
昔の駅ビルは解体されて残っていない。
まだ、工事中の場所のあるが、姫路城の案内に向かって歩く。

北口へ出ると、大手前通りがお城まで続いている。
左の神姫バスのターミナルの前の横断歩道を渡り、バス山陽百貨店の前の歩道を歩く。

一つ目の交差点を左に曲がる。
中国銀行を正面に見ながら、コンビニ(セブンイレブン)の前を左に曲がる。
一方通行の4車線道路。

道に沿ってまっすぐ歩く。
神社や映画館も通り過ぎる。

道路向かいの右手に大きな白い建物(姫路信用金庫本店)が見えてくると、もうすぐ到着。

隣に、関西電力の姫路支店がある。
その道路向かいのビルが目的地。

ゼンリンの緑の看板が出ている。

工事中でした。
阿部 謹也 著 『世間とは何か』 を読む

序章 「世間」とは何か
世間の掟
世間には厳しい掟がある。それは特に葬祭への参加に示される。その背後には世間を構成する二つの原理がある。
一つは、長幼の序であり、もう一つは贈与・互酬の原理である。
贈与・互酬とは、対等な関係においては貰った物に対してはほぼ相当な物を贈り返すという原理である。
世間には会員名簿などはない。したがって誰が自分の世間に入っているかは必ずしもはっきりしないが、おおよその関係で解るのである。
世間を騒がせたことに謝罪する
「世間」の構造に関連して注目すべきことがある。
世間は社会ではなく、自分が加わっている比較的小さな人間関係の環なのである。自分は無罪であるが、自分が疑われたというだけで、自分が一員である環としての自分の世間の人々に迷惑がかかることを恐れて謝罪するのである。日本人は自分の名誉より世間の名誉の方を大切にしているのである。
世間がなくなってしまったら
日本人は長い間世間を基準として生きてきた。世間の内部では競争はできるだけ排除されている。したがってあまり有能とはいえない人でも、その世間の掟を守っている限りそこから排除されることはない。
私達は個人と個人の付き合いに慣れていない。日本の個人はすべて世間の中に位置を持っているから、初対面の人の場合では、いったいどういう世間に属しているかが問題になる。(出身地、出身校、会社、地位)
世間が違いすぎると親しくなる可能性は低いのである。
欧米人は日本人のことを権威主義的という。権威主義とは、自分以外の権威に依存して生きていることをいうのである。何らかの意見を聞かれたときに、自分の意見をきちんということが大切であるが、他の人の意見を聞きながら自分の意見をそれに合わせたりすることをも権威主義的と呼ばれるのである。
坊ちゃんと赤シャツ
世間の中での個人の位置はどのようなものなのかという問いが浮かぶ。
私達は明治以来長い間個性的に生きたいと望みながら、十分な形で個性がのばすことができなかった。そのことは、この百年の間ロングセラーとして読み続けられている夏目漱石の「坊ちゃん」を見ればすぐに解ることである。
「坊ちゃん」はイギリスでヨーロッパにおける個人の位置を見てしまった漱石が、わが国における個人の問題を学校という世間の中で描き出そうとした作品である。
赤シャツは、あるとき坊ちゃんにいう。「あなたは失礼ながら、まだ学校を卒業したてで、教師は始めての、経験である。所が学校と云うものは中々情実のあるもので、さう書生流に淡白には行かないですからね。」
坊ちゃんはそれに対して「今日只今に至る迄是でいいと固く信じて居る。考えて見ると世間の大部分の人はわるくなる事を奨励して居る様に思ふ。わるくならなければ社会に成功はしないものと信じて居るらしい。たまに正直な純粋な人を見ると、坊ちゃんだの小僧だのと難癖をつけて軽蔑する。それじゃ小学校や中学校で嘘をつくな、正直にしろと倫理の先生が教えない方がいい。いっそ思い切って学校で嘘をつく方法とか、人を信じない術とか、人を乗せる策を教授する方が、世の為にも当人の為にもなるだろう。」と考えている。
「坊ちゃん」は学校という世間を対象化しようとした作品であり、読者は坊ちゃんに肩入れしながら読んでいるが、その実皆自分が赤シャツの仲間であることを薄々感じ取っているのである。しかし世間に対する無力感のために、せめて作品の中で坊ちゃんが活躍するのを見て喝采を叫んで居るにすぎないのである。
非言語系の知
私達は学校教育の中で西欧の社会という言葉を学び、その言葉で文章を綴り、学問を論じてきた。しかし、文章の中で扱わないことを会話と行動においては常に意識してきた。
いわば世間は、「非言語系の知」の集積であって、いままで顕在化する必要がなかった。
明治10年(1877)にsocietyの訳語として「社会」という言葉が作られた。そして同17年頃にindividualの訳語として「個人」という言葉が定着した。それ以前にはわが国には「社会」「個人」という言葉がなく、現在のような意味の「社会」「個人」という概念もなかった。
それまでは、「世の中」「世」「世間」という言葉があり、時には現在の「社会」に近い意味で用いられることもあった。
欧米の社会という言葉は本来個人が作る社会を意味しており、個人が前提であった。欧米の意味で個人が生まれていないのに社会という言葉が通用するようになってから、少なくとも文章のうえではあたかも欧米流の社会があるかのような幻想が生まれたのである。
しかし、学者や新聞人を別にすれば、一般の人々は「社会」という言葉をあまり使わず、日常会話の世界では相変わらず「世間」という言葉を使い続けたのである。
日本の個人は、世間向きの顔や発言と自分の内面の想いを区別してふるまい、そのような関係の中で個人の外面と内面の双方が形成されているのである。いわば個人は、世間との関係の中で生まれているのである。世間は人間関係の世界である限りでかなり曖昧なものであり、その曖昧なものとの関係の中で自己を形成せざるをえない日本の個人は、欧米人からみると、曖昧な存在としてみえるのである。ここに絶対的な神との関係の中で自己を形成することからはじまったヨーロッパの個人との違いがある。
高橋 源一郎 著 『ニッポンの小説 百年の孤独』 ちくま文庫 を読む
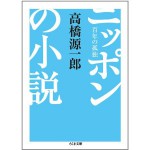
「ニッポンの近代文学、百年の孤独」(プロローグ)
19世紀後半、封建的な世界が崩壊して、新しい政府が誕生した時、この小さな東の国は、とてつもない変化を被ることになりました。そして、生き残るために、西洋社会の文物を輸入されました。かくして、科学技術や社会システムが、そして文化が輸入されました。その中にはもちろん、「文学」も含まれていました。
重訳というのはとても興味がある現象です。一つの言語から、もう一つの言語へ、そこからさらに次の言語へと、移し変えられる度に、元の言語が持っている困難さはすり減っていき、言葉は透明になり、伝えやすいものだけが伝わることになります。あるいは、誰にでも使える言葉へと変わっていきます。
もちろん、ここでもベンヤミンが「翻訳者の使命」と呼んだ、あの有名なフレーズは有効です。
「ある容器の二つの破片をぴたりと組み合わせて繋ぐためには、両者の破片が似た形である必要はないが、しかし細かな細部に至るまで互いに噛み合わなければならぬように、翻訳は、原作の意味に自身を似せてゆくのではなく、むしろ愛をこめて、細部に至るまで原作の言いかたを自身の言語の言いかたのなかに形成してゆき、その結果として両者が、ひとつの容器の二つの破片、ひとつのより大きい言語の二つの破片と見られるようにするのでなくてはならない。」
ベンヤミンの、翻訳に関するこの断言は、おそらく、完成した言語、長い伝統の果てに成立した言語間の受け渡しについていわれたものです。しかし、そうではなく、完成した言語から、新しい言語へ、未だ始まっていない言語への受け渡しにこそ、この断言は、より一層あてはまるような気がするのです。そこでは、単に一つの作品から、もう一つの作品へ「翻訳」が行われるのではなく、「翻訳」を通して、規範となる「文」そのものが、元の言語の反対側に産みだされるのです。
「ニッポン近代文学」という集落で話されてきた言語は、国木田独歩の「文」、それにの先駆たる、二葉亭四迷の「文」から流れ出たものです。それは、ほとんど変化することはありませんでした。
不思議なのは、「ニッポン近代文学」という集落は、実に多くの「外部」の侵食を受けているのに、つまり、外国文学や、文学以外のさまざまなものに影響を受けてきたのに、孤立しているように見えることです。
ところで、「文学」とは何でしょうか。
「文学」とは、遠くにある異なったものを結びつける、あるやり方のことです。なぜなら、「文学」は、言語だけで出来ていて、しかも、言葉とは、要するに、遠くにある異なったものを結びつけるために出来たからです。
言葉は、物と観念を結びつけます。名前と事象を結びつけます。存在しないものと存在するものを結びつけます。関係づけることが不可能に見えるものを、いとも簡単に関係づけます。
我々がコミュニケートするためには、言語が必要なのです。もちろん、言語以外にも、コミュニケートするツールはあります。映像がそうです。貨幣もそうです。いや、貨幣は言語そのものなのです。そして、資本主義社会では、貨幣も言葉も、絶えず価値の変動に晒されなければならない、というわけです。
だから、『資本論』に「文学」の一切が書いてるということもほんとうです。言葉というものが、どうやって産み出され、異なった共同体をどう結び付け、どう流通し、それが集まって巨大な塊になり、その結果、一つ一つの言葉を抑圧するようになるのか、それらはすべて、あの本の中に書いてあるのです。
二葉亭四迷が作った「器」に、若者たちが「文学」を充填しはじめる時が来ました。
いくつもの言語が存在するということは、つまり、翻訳というものが必要であるということは、「器」は絶えず壊れ、それ故、絶えず修復されなければならない、ということを意味している。
言葉が混乱の只中に陥った時、はじめて、我々は「文学」を必要とするようになった。「文学」とは、「器」を作り、そして壊す、その一連の行いそのものではないでしょうか。
桜井 英治 著 『贈与の歴史学』を読む。
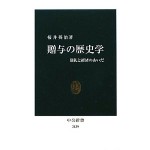
日本の贈与は義務感にもとづいてなされる傾向がつよい。日本の民法が西欧諸国のそれと異なり、贈与の撤回を認めていないのもそのためだ。
そのような贈与のあり方は、日本の歴史の中で中世、鎌倉・室町時代(12世紀から16世紀)、武士が新たな支配階級として勃興してきた時代までさかのぼる。この時代、極端な功利的性質を帯びるのである。
中世は自給自足の時代などではなく、多くの商品が流通し、それらの需要と供給のバランスによって決定される市場経済が成立していた。
京都には、土倉とよばれる多数の金融業者が店舗を構え、貸出だけでなく、大口小口の預金者から資金を集め、営業利益に応じて利息を払うという、銀行さながらの業務をおこなっていた。また、権利(物権、債権)が中世ほど容易に移転しえた時代は少ない。一片の借金証文が債務者の知らないうちに金融業者間で転売され、いつの間にか見ず知らずの債権者の手に渡っているなど普通におこりえた。
市場経済にみられた合理的思考や計算、打算といった観念は、贈与の領域にも深く浸透していた。
思うに贈与経済と市場経済とは、一般に信じされているほど対立的なものではないのだろう。対立的に見えるのは、未開社会と近代資本主義社会しか分析せず、その中間に位置する多様な社会の分析を省いてきたことからくる偏見である。
贈与の功利的性質とか市場経済との親和性への反論は、、純朴な贈答が典型的な贈与の姿であるというもの。
この反論は、半分は正しく、半分は間違っている。ある時代のもっとも進んだ部分が、次の時代に跡形もなく消え失せてしまうことは、歴史にはしばしばおこりうる。
同じ贈与慣行のなかにも時代によって変わるものと変わらないものがある。かつて、フェルナンド・ブローデルは、人類の中長期的な歴史の営みを下層のもっとも変化の緩慢なステージから順に「物質文明」「市場経済」「資本主義」という三層構造として概念化したが、贈与の歴史においても参考になる。主に民俗学が注目してきた食品の贈答が「物質文明」の層に関わる事象とすれば、本書は、「資本主義」の層に相当する。そこに見られる贈与の振る舞いは自由奔放で、限りなく商取引に近づくが、それでも両者が完全に同化してしまうことだけはついになかった。最後まで踏み越えられることのなかったこの一線こそ、贈与を贈与たらしめている原理の心髄が潜んでいる。
1.4つの義務
マルセル・モースの問い
フランスの社会学者マルセル・モースの『贈与論』の中で、贈与をめぐる義務として次の三つをあげた。
「お返しの義務」
贈答という言葉自体が返礼(答)の存在を前提にしている。このようにそっれを受け取った者に対して返礼を義務づける贈与の性質を互酬性(reciprocity)とよぶ。贈り物を一種の債務・負債と感じる意識がある。平たくいえば、贈り物を受け取ることにより受贈者には「借り」ができ、贈与者には「貸し」ができる。このような債務意識はどこから来るのか。
「贈り物を受ける義務」
贈り物を受け取ることにより、受贈者には贈与者に対する「借り」ができる。贈与者は、-ときに意識的に、ときに無意識に―その受贈者が自分と特別な人現関係を築いてくれることをもって回収しようとする。受贈者は、その期待に応えてもよいと思えば素直に受け取るだろうし、期待に応えられないと思えば受け取らないか、かりに受け取ったとしても、その期待とは別の対価で返済をおこなうだろう。要するに、人は返済のできる見込みのない「借り」をつくりたくないのである。
個人と個人、あるいは集団と集団が良好な関係を構築・維持しようとするとき、「贈り物を受ける義務」は、もっとも基本的なマナーとなった。
「提供の義務」
この種の贈与を強いるメカニズムは、表面的にはヴァランタリーな体裁をとっている場合でも、実際には暗黙の圧力・義務感のもとで贈られることがおおい。「贈り物を与える義務」の場合、贈与者-受贈者間だけでは完結せず、そこに比量の対象となる他者(同僚や同業者)が登場する。そして、受贈者で実際に同格他者との比較が行われるか、実際に行われないまでも、そのような比量がおこなわれることを恐れる気持ちが贈与者に萌しさえすれば、それはいつでも義務となる。
「神に対する贈与の義務」
神頼みも無償ではかなえてもらえないわけだが、必ずしも多額である必要はない。
2.神への贈与
神に対する贈与が税に転化した例として、古代の祖と調があげられる。
「祖」
祖が土地からの収穫物の一部を初穂として神の代理人たる首長に貢納する慣習から生じた。そして、「未開社会」において「初穂または田祖は、首長(または共同体)の支配する領域の土地を用益する民戸の帰属を確認する最低限の義務であった。」
「調」
古代には毎年9月に伊勢神宮に初穂を奉る神嘗祭、11月に畿内諸社に初穂を奉る相嘗祭(後の12月の月次祭)、2月に全国の官社に幣帛を分かつ祈年祭という3つの重要な祭儀があったが、これらの初穂、幣帛に用いられたのが調である。
これら初穂。幣帛の内訳は繊維製品や海産物、酒、塩など調の品目と一致する。調の納期は、近国が8月中旬から10月末、中国が11月末、遠国が12月末であるのを受けたものである。
海産物の調が主に加工品であったのに対して、生鮮品を含む海産物を天皇の食事用に貢納した制度を贄というが、これも本来は神への捧げものであった。
「初穂・初尾」
農業や漁業から得られた最初の収穫物、初物のことで、初穂は神仏に捧げるべきものとされ、語自体も現代にいたるまで語義を変えずに用いられている。初穂は自然界から得られた恵みの一部を神仏に捧げるものであり、同様の捧げものは汎世界的に見出すことができる。
「人は、聖なる存在から受け取ったものの小部分を、聖なる存在に与え、しかも、自分が与えるもののすべてを、それから受け取るのである。」というのがその本来の意義であった。
3.人への贈与
人に対する贈与が税に転化した事例を見る。
室町幕府は、経済先進地帯である京都に本拠地を占めたことから、総じて土地や農業からの収益よりも、商業・流通・金融・貿易などに大きな比重をおいていた財政の特徴がある。
守護出銭とは、大小守護たちが将軍家に拠出した分担金にほかならない。守護出銭は、将軍家が大きな支出に直面した際に守護が臨時に拠出したもので、賦課方法は、諸大名が将軍に申し出るかたちでおこなわれた。
贈与の強制力
1.有徳思想
有徳銭の起源のひとつは、諸社の祭礼を挙行するために特定の有徳人を指名して祭礼費用を拠出させる馬上役のシステムにあったと考えられる。中世の京都では、五条以北を祇園社と六条以南を稲荷社がそれぞれの祭礼圏として分け合っていた。12世紀の京都には、大きな繁華街が、四条と七条の二か所に形成されており、多くの有徳人を生み出した。馬上役は、この祭礼圏に居住する有徳人の中から「闕(けち)」のあったものを差定する方式をとった。
貧しい民衆に代わって有徳人が祭礼費用を負担し、その祭礼を民衆が享受する。有徳人に徳行を求める民衆意識こそ、中世後期において有徳銭をささえていた主要な倫理的基盤であった。
徳性一揆(土一揆)
有徳銭が民衆に対する間接的な贈与であったとすれば、土倉・酒屋などの金融業者に債務破棄を求めた徳性一揆は、いわば民衆にたいする直接的贈与を求めた運動と位置づけられる。
2.「例」の拘束力(先例・新儀・近例)
中世においては「先例」、すなわり昔から連綿と続いてきたことこそが一般に<善いこと>とされた。その対義語が「新儀」であり、前例のない新しいことを意味した。前例のないことは一般に<悪いこと>と考えられていた。「新儀」が「先例」になるケースとして、それをおこなった人物が彼の家や所属集団に繁栄をもたらすなど、あやかるべき生涯を送った場合であり、彼の「新儀」は、「佳(嘉)例」と呼ばれ、準拠すべき「先例」に転ずる。
もう一つのケースとして、「新儀」が現に何度か続いて行われてしまうことによって、それが既成事実化して「先例」になることもあった。このような日の浅い「先例」のことを「近例」という。「新儀」の恩恵に浴している者はその「先例」化を願い、そうでない者は「先例」を守るためにこれを斥けようとするせめぎあいが、「近例」というステージで戦われた。
3.「相当」の観念と「例」の秩序
「先例」の拘束力は贈り物の品目や数量に及んだ。前と異なる品目を贈ったり、品目は同じでも数量を減らしたりすれば、受贈者側は不満を覚え、ときにはあからさまな抗議に出たこともあった。
「相当の儀」
対人関係において譲れるか譲れないかの判断基準を提供していたのが「相当」とよばれる概念である。
中世の人びとは損得勘定、釣り合いということに非常に敏感であった。彼らは、損得が釣り合っている状態を「相当」、釣り合ってない状態を「不足」とよび、他家との紛争や交際ではつねに「不足」の解消と「相当」の充足を求めた。
贈与における「相当」
何よりもまず、贈り物と返礼が同じものか、少なくとも等価値であることが不可欠である。これを人類学では、対称的返済とか同類交換の原理とよぶ。中世にもいつのころからか夏の恒例行事として瓜を贈りあう習慣が生まれたが、この季節にはどこの家にも瓜が溢れていると知りながら、人びとは瓜を贈り、また受け取りつづけたのである。
贈与と経済
1.贈与と商業
13世紀後半、米で納められていた年貢が、このころを境にして銭で納める形態に変化したのである。これを代銭納制というが、中世日本の経済にとって最大の事件であった。
代銭納制がはじまると、生産物を現地でいったん売却・換金し、それによって得た銭を年貢として中央に送る。生産物は、銭に変えられた時点で商品に変化する。つまり、代銭納制普及以後の日本列島では本格的な市場経済が展開した。
銭よりもさらに軽量で輸送コストの安い決済手段が求められた結果、この時期に出現したのが「割符(さいふ)」とよばれた手形である。
割符には、1個10貫文(今日の100万円)の定額手形が多く、それらは一つ、二つと個数で数えられ、一つといえば10貫文、二つといえば20貫文を指し、定額面であることから人から人へ転々と譲渡されうる紙幣的な機能が期待されていたことを示している。
代銭納制の普及は、商品作物の生産を促した可能性も高い。土地土地の気候に適した、しかも換金性のより高い作物、つまり商品作物を作ったほうがはるかに効率的なわけで、そのような生産者行動を制度的に可能にした。
2.贈与と信用
対称的返済、同類交換の原理が優越していた日本の贈与においては、財政や家計の状態にかかわりなく、つねに贈答品の交換価値に人びとの強い関心が向けられた。
贈り物の使用価値が重視されないのであれば、もはや現物で贈与をおこなう必要はなく、純粋に交換価値だけを運ぶ物品を贈りあえばよいということになる。ここに、交換価値の伝達を唯一の機能とし、それ以外の使用価値をいっさい脱ぎ捨てた物品、すなわち貨幣による贈与がはじまる必然性があった。現金が平気で贈答されることについて、日本の特殊性として指摘されるところだが、中世後期の日本も銭を贈答に用いることにまったく抵抗を示さなかった社会である。
贈り物を持参するさいに折紙(目録)を添える作法があり、銭の贈答の場合も同様であった。贈り物一般に添える折紙を「進物折紙」、銭の添える折紙を「用脚折紙」「鳥目折紙」などとよんだが、もともと儀礼の道具にすぎなかったこれらの折紙が銭の贈答をめぐる計算上の操作に利用された。
用脚折紙には、品目(銭)は書かず、金額だけを「疋」単位で記すことに特徴がある。一疋とは十文のことで、五百疋は、五貫文である。
「疋」というのは、もともと絹の長さの単位だったものが銭の単位に転用されたもので、かつて絹が貨幣として用いられた時代の名残である。12世紀から13世紀にかけて絹の貨幣機能が銭に奪われていくにしたがって、「疋」という単位も絹から銭に引き継がれたのだが、注目されたのは、贈答のような儀礼的な面では「文」や「貫文」ではなく、「疋」を使うのが一般的だった。「疋」はまさに儀礼用単位に特化した。
「折紙の使い方」
いきなり現金を贈ることはせず、まず金額を記した折紙を先方に贈り、現金はあとから届けるのが普通であった。
次に現金が引き渡されたあとで、折紙は清算が済んだ証として受贈者から贈与者に返却された。もっとも簡略な方法は、折紙の金額部分に合点を付して返却するというものである。より手の込んだ方法として、「裏封」といって折紙の裏面に受取文言を記載して返却する方法もあった。
「折紙の経済的機能」
折紙のシステムが贈与者にもたらした第一の利点は、資金の準備がなくても贈与がおこなえるようになったことである。
現金は用意できなくても、折紙を贈ることでとりあえずその場をしのげるようになった。
「贈与の相殺」
折紙を利用した計算上の操作として、もっとも典型的なのが贈与の相殺である。折紙のシステムによって贈答というすぐれて儀礼的な分野にも債権・債務関係と同様の操作が入り込んできた。とくに相殺という手段は、現金の移動がいっさいなく、帳面上の操作、計算のみによって贈与を完結させてしまう点で、贈与の存在意義を根本から脅かすものだった。