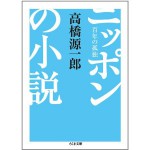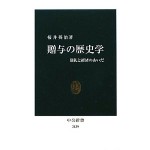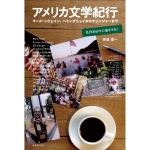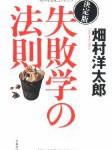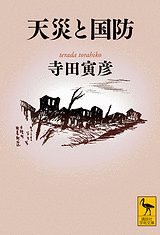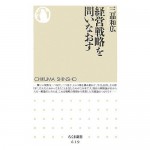桜井 英治 著 『贈与の歴史学』を読む。
贈与の歴史学 日本の贈与は義務感にもとづいてなされる傾向がつよい。日本の民法が西欧諸国のそれと異なり、贈与の撤回を認めていないのもそのためだ。
1.4つの義務
マルセル・モースの問い
贈り物を与える義務(提供の義務)
それを受ける義務(受容の義務)
お返しの義務(返礼の義務)これに、モーリス・ゴドリエによって、くわえられた第四の義務
神々や神を代表する人間へ贈与する義務(神に対する贈与の義務)
「お返しの義務」
「贈り物を受ける義務」
「提供の義務」
「神に対する贈与の義務」
2.神への贈与
「祖」
「調」
「初穂・初尾」
3.人への贈与
贈与の強制力
徳性一揆(土一揆)
2.「例」の拘束力(先例・新儀・近例)
3.「相当」の観念と「例」の秩序
「相当の儀」
贈与における「相当」
贈与と経済
2.贈与と信用
「折紙の使い方」
「折紙の経済的機能」
「贈与の相殺」